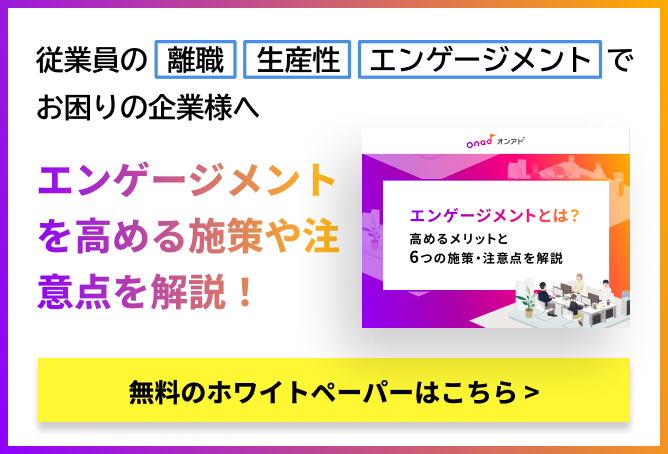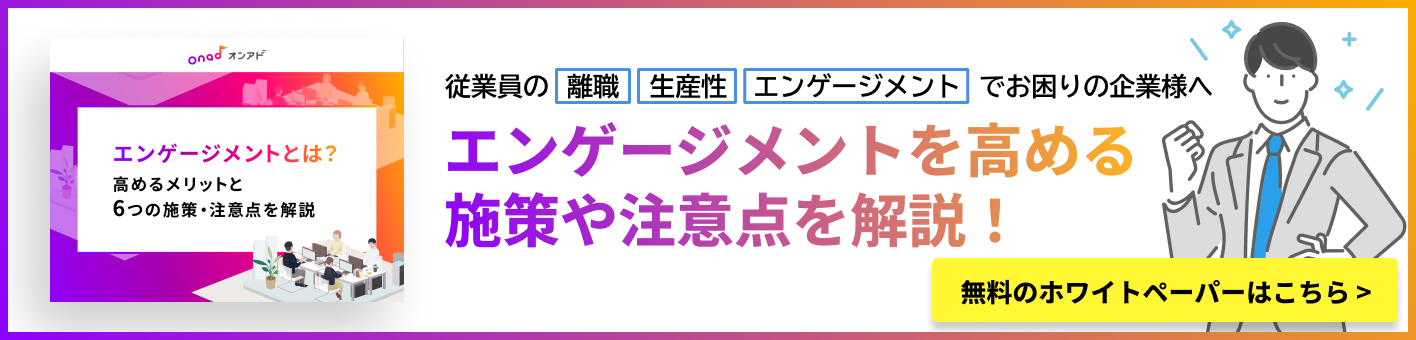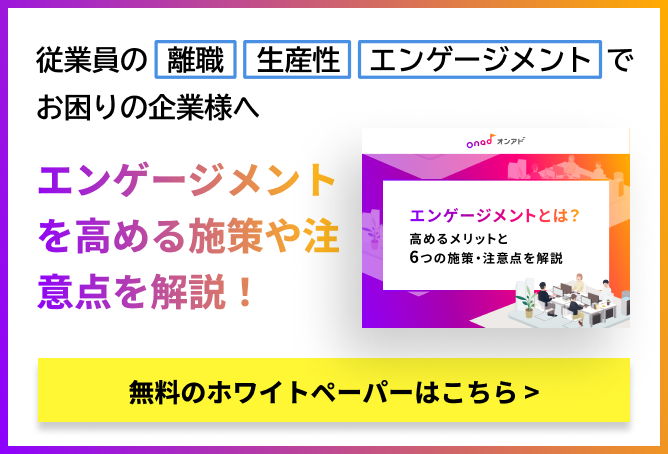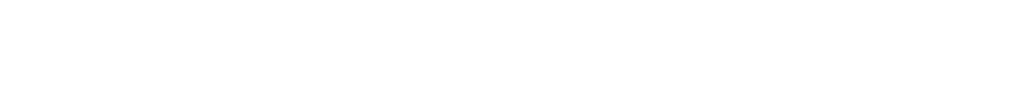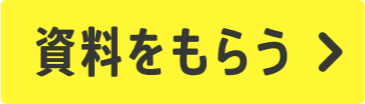SHARE
SHARE
ウェルビーイング・健康経営それぞれの概要や目的|両者の違いについても解説
ウェルビーイング |
自社の経営や福利厚生の見直しを検討する際、ウェルビーイング経営や健康経営という言葉を耳にした人も、少なくないでしょう。
本記事では、ウェルビーイング経営や健康経営を取り入れるために情報収集している人に向けて、それぞれの概要や両者の違いなどを解説します。ウェルビーイング経営や健康経営に取り組むメリットや施策例も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
日本におけるウェルビーイング・健康経営の現状
ここでは、日本でウェルビーイングや健康経営が広まったきっかけや、現在の状況を解説します。
ウェルビーイング
ウェルビーイングは、2021年に閣議決定された科学技術基本計画で方針が明確化されました。また、子供・若者育成支援推進大綱にも、ウェルビーイングについて明記されています。2021年は「ウェルビーイング元年」ともよばれ、現在では日本でも業種を問わず、ウェルビーイング経営を実践する企業が増えています。
健康経営
コロナ禍を経て健康経営が認知されるようになり、その重要性に注目が集まるようになりました。実際に、健康経営に取り組む企業も増加傾向にあります。健康経営の取り組みは大企業で多くみられますが、現在では小規模企業でも実践する企業が増えています。
ウェルビーイング経営の基礎知識
ウェルビーイング経営とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。以下で、概要や目的を解説します。
ウェルビーイング経営の概要
ウェルビーイング経営とは、自社の利益追求のみを目的とせず、企業の関係者全員の幸せを追求する経営方法のことです。ウェルビーイング経営は、従業員個人に注目するだけでなく、組織としての在り方にも注目します。なお、ウェルビーイング経営に重要なのは、定義付け・具体化・可視化の3つの視点とされています。
ウェルビーイング経営の目的
ウェルビーイング経営は、企業のパーパス(存在意義)を実現することが一つの目標となります。また、パーパスを実現するためには、単なる利益追求だけでなく、社会への貢献や従業員の健康や幸福の実現が必要です。ウェルビーイング経営では、従業員が健康で病気にならないのはもちろんのこと、目的意識を持って積極的に働ける状態を目指します。
健康経営の基礎知識
ウェルビーイング経営と似たものに健康経営がありますが、こちらはどのようなものなのでしょうか。
健康経営の概要
健康経営とは、従業員の健康を経営課題として考えて戦略的に管理する方法のことです。従来は、従業員それぞれが健康管理を実施していました。しかし、従業員の健康状態が企業全体に与える影響について見直されるようになり、健康経営の実施は企業の成長につながる投資とみなされるようになりました。
健康経営の目的
健康経営の目的は、従業員の健康を管理し、いきいきと業務を遂行できる状態をつくることにあります。そしてその結果は、企業価値の向上にもつながります。また、健康経営の実施は、人材への投資を進めている企業であることを、社外の投資家や求職者へアピールすることにもつながるでしょう。
ウェルビーイング・健康経営の違い
ウェルビーイング経営と健康経営は、どちらも会社経営に重要なものです。以下では、これらにどのような違いがあるのかを詳しく解説します。
ゴール
ウェルビーイング経営は、従業員の健康の先にある働きがいの実現がゴールの一つです。さらに、営業利益以外の社会的な貢献もゴールとなりえるでしょう。対して健康経営は、従業員の健康を維持したり向上させたりすることで、生産性を向上させることが主たるゴールです。
視点
ウェルビーイング経営は、従業員の視点やステークホルダーの視点も加味して、社会的に満たされた状態を追求する経営手法をいいます。一方で健康経営は、企業の視点から従業員の健康増進を支援する経営手法です。
推進方法
ウェルビーイング経営は、経営で目指すべき姿はなにかに重点をおき、推進していきます。企業のパーパスはもちろん、従業員それぞれの価値観を考慮する必要があるため、施策の内容は企業によって異なるでしょう。
健康経営は、従業員の健康維持向上による、生産性の向上に重点をおいて推進していきます。推進方法としては、健康診断の実施や運動系のサークル活動の促進などが挙げられます。
ウェルビーイング・健康経営が注目される背景
なぜ近年、多くの企業がウェルビーイング経営や健康経営に注目しているのでしょうか。以下で詳しく解説します。
労働人口が減少している
近年、日本の労働人口は、女性が増加傾向にあるものの、全体でみると減少しています。今後も少子化が進むことで、日本の労働人口は減少すると考えられています。
労働人口がさらに減っていく可能性を踏まえると、企業の労働力確保は急務です。また、人材の確保だけでなく、限られた従業員の能力を最大限に引き出すことも、重要だと考えられるようになりました。そのため、こうした事態を打開するための手法として、ウェルビーイング経営や健康経営が注目されるようになっています。
働き方や価値観が多様化している
新型コロナウイルス感染症の流行や、政府が推し進める働き方改革などを背景に、従業員の働き方や価値観が多様化しました。
ウェルビーイング経営や健康経営は、多様な価値観や副業・テレワークなどさまざまな働き方を受け入れながら、帰属意識や働きがいを高める手法とされています。働き方や価値観の多様化に対応するための手法として、ウェルビーイング経営や健康経営に注目が集まるようになりました。
心身不調者が増えている
近年、心身の不調から長期間休職や退職する人が増えています。厚生労働省による令和4年度の労働安全衛生調査によると、メンタルヘルス不調による連続1月以上の休職者や、退職者がいた事業所は13.3%です。そのため、ストレスの軽減や、精神的不調による休職後の仕事の復帰支援などに関する施策の重要性が増しています。
そこで、従業員の健康や幸福を追求するウェルビーイング経営や健康経営に、注目が集まっています。
参考:厚生労働省 令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
SDGsが注目を集めている
SDGsとは、持続可能な開発目標の略語であり、企業による取り組みが注目されている概念の1つです。経営理念や事業目標にSDGsの達成を盛り込む企業も増えています。
SDGsの目標の1つに「全ての人に健康と福祉を」があり、その達成に効果的な経営手法としても、ウェルビーイング経営や健康経営に注目が集まるようになりました。
ウェルビーイング・健康経営に取り組むメリット
ウェルビーイング経営や健康経営に企業が取り組むことで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
生産性や業績の向上
従業員が健康な状態で活力に満ち、幸福感をもって仕事ができていると、ストレスが溜まりにくく、パフォーマンスが上がったり仕事への意欲がより高まったりするでしょう。その結果、欠勤したり休職したりする従業員が減少して、生産性が向上するとされています。
離職率の低下
ウェルビーイング経営・健康経営が正しく機能し、従業員の心身の健康を保つことができれば、離職率も低下するでしょう。離職率の低下によって人材が定着することで、自社の商品やサービスの質が保たれるようになります。また、従業員の幸福度が高い企業では、従業員の自社への帰属意識が高まるため、離職率を下げることにつながります。
企業イメージの向上
ウェルビーイング経営や健康経営の実践は、社内への影響以外にも、自社のブランドイメージの向上につなげられるでしょう。例えば、従業員の心身の健康を大切に考えているという企業イメージがあれば、求職者に好影響を与えられます。求職者にとって魅力的な企業であれば、採用活動も活発化し、人材確保の問題解決にもなるでしょう。
従業員のウェルビーイング・健康を増進する施策例
ここでは、従業員のウェルビーイング・健康を増進する施策を紹介します。自社の取り組みや福利厚生、人事制度などの参考にしてください。
福利厚生の充実
従業員の食生活や住宅に関する福利厚生制度を充実させます。福利厚生を充実させると、従業員の身体的・精神的健康が向上するでしょう。例えば、食生活改善の指導の導入や、食堂で健康を意識したメニューを提供することなどが考えられます。
社内コミュニケーションの促進
社内コミュニケーションが活発になれば、同僚や上司との関係性が改善するでしょう。また、従業員の心身の不調を早期に発見できるようにもなります。施策としては、チャットツールの導入や、社内イベントの実施などが挙げられます。
就業環境の改善
従業員が働きやすい環境を整えます。環境改善のためには、労働時間を見直したり、ノー残業デーを設けたりすることがおすすめです。また、副業支援やテレワークの導入なども環境改善につながります。
ハラスメントの防止
ハラスメントは、メンタルヘルスの悪化や離職の原因になります。そのため、ハラスメントをなくすことを社内で明確に打ち出し、働きやすい環境を構築しなければなりません。ハラスメント対策としては、研修の実施や相談窓口の設置、ハラスメント防止宣言などを検討するとよいでしょう。
健康状態のチェック
システム上での問診や、測定データをもとにした健康状態の分析、アドバイスが自動でできるシステムを導入し、自身の健康を意識してもらう取り組みも効果的です。また、従業員の運動を促進する取り組みとして、万歩計で歩数を集計・発表する取り組みなども、健康意識の向上につながるでしょう。
運動の促進
社内で運動機会を設け、健康への取り組みを積極的に行いましょう。例えば、昼食後の歩行運動の実施やスポーツジムとの法人契約などが考えられます。運動不足解消のために、運動器具を従業員に配布するのもよいでしょう。さらに、マラソンやソフトボールなどの運動大会への参加補助や社内運動会の開催も、健康意識を高めるきっかけづくりになります。
まとめ
ウェルビーイング経営および健康経営は、従業員の健康を維持する以外にも、多くの効果があります。従業員のウェルビーイング・健康度が高まれば、モチベーションが高まり、生産性の向上にもつながるでしょう。またこれらの取り組みを積極的に行っている事実は、社外へのアピールにもつながります。
ウェルビーイング経営・健康経営を検討中の方は、株式会社オンアドにぜひお問い合わせください。オンアドでは、「従業員のお金の悩み解決」を通じて企業の成長をサポートする「お金の福利厚生サービス」を提供しています。ご関心をお持ちの方は、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。