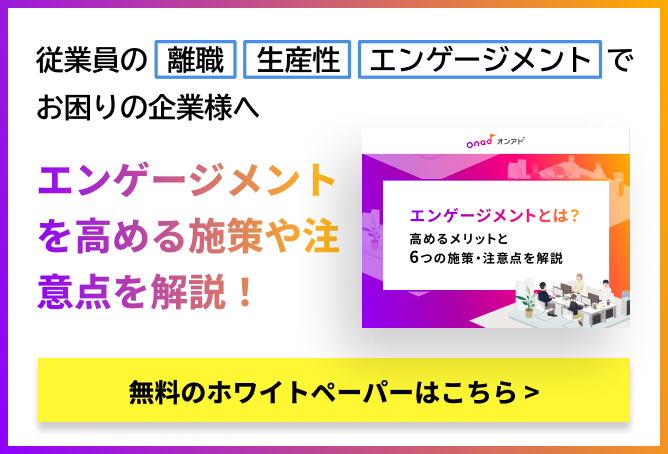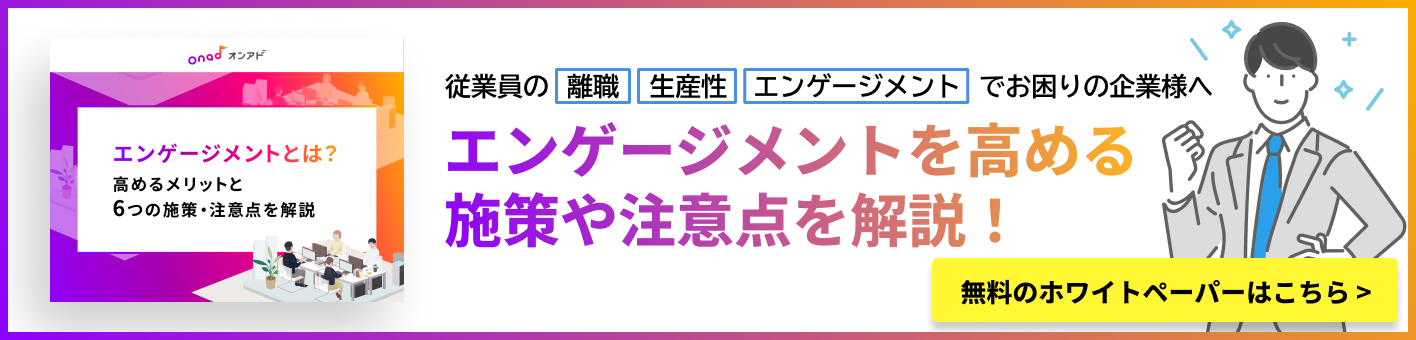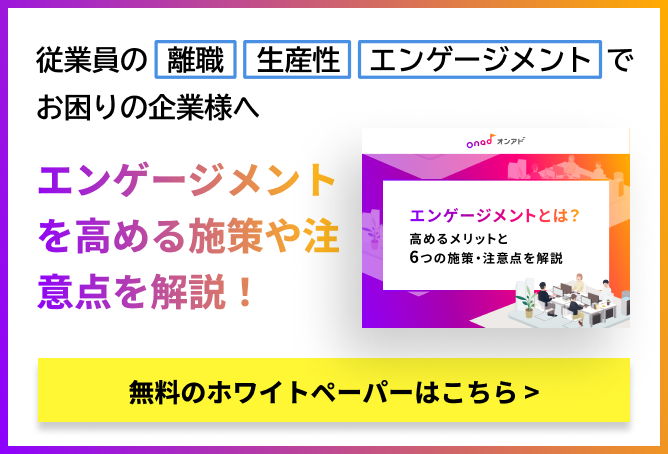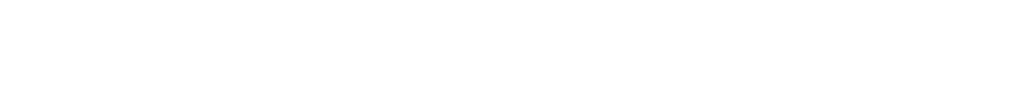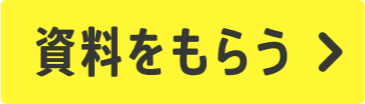SHARE
SHARE
ウェルビーイングとは?考え方や取り組むメリットについて解説
ウェルビーイング |
従業員によりよい環境で働いてもらうためには、ウェルビーイングの考え方を経営い取り入れることが効果的です。しかし、ウェルビーイングとは一体どのような考え方なのか、詳しくはわからないという人もいるのではないでしょうか。
本記事では、ウェルビーイング概念の概要や、それを取り入れた経営手法である「ウェルビーイング経営」の基本的な考え方などについて解説します。ウェルビーイングについて詳しく知りたい人は、参考にしてください。
目次
ウェルビーイングとは
ウェルビーイングとは、幸福で身体的、精神的、社会的すべてにおいて満たされた状態を指す言葉です。ウェルビーイングの基本的な概念は、1946年に世界保健機関(WHO)憲章の前文で定義されています。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
(健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的、精神的、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることを指します)。
ウェルビーイングとエンゲージメントの違い
ビジネスシーンにおけるウェルビーイングと似た言葉に「エンゲージメント」がありますが、双方の違いは考え方の視点にあります。ウェルビーイングが従業員の仕事や私生活など多面的な要素に着目した幸福感を示す概念であるのに対し、エンゲージメントは従業員と企業の関係性に焦点を絞った概念です。
ウェルビーイングとウェルネスとの違い
ウェルネスとは、一般的に心身の健康を表す言葉です。ウェルビーイングも健康を内包した概念ではありますが、ウェルネスは身体的な健康に重点を置く一方、ウェルビーイングは幸福度を多面的な視点で捉える概念です。
ウェルビーイング(幸福感)は4つの因子で構成される
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の教授である前野隆司氏は、ウェルビーイング(幸福感)には4つの因子があると述べています。4つの因子の内容は、以下のとおりです。
第1因子:自己実現と成長の因子(やってみよう因子)
第2因子:つながりと感謝の因子(ありがとう因子)
第3因子:まえむきと楽観の因子(なんとかなる因子)
第4因子:独立とマイペースの因子(あなたらしく因子)
出典:幸福度の推奨アンケート(SWLS、幸せの4因子など)についてl
ウェルビーイングが注目される背景
ここでは、ウェルビーイングが注目される背景について解説します。
価値観の多様化
現代社会では、幅広い考え方やバックグラウンドを持っている人が一緒に働くようになっており、価値観の多様化が進んでいます。経営においても、従業員の多様性を尊重することの重要性やその効果に対する理解が高まっていることから、ウェルビーイングが注目されています。
労働環境の変化
近年は、ワークライフバランスが重視されるようになってきました。リモートツールの普及もあり、時間や場所にとらわれない働き方を希望する従業員も増えています。従業員のライフスタイル・ライフイベントに応じた柔軟な働き方を提供し、結果として企業の生産性向上などに繋げていくという観点で、ウェルビーイングの考え方が注目されています。
SDGsでの言及
SDGsとは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すために定められた、全17項目から成る国際的な目標です。3つ目の目標である「すべての人に健康と福祉を」が、ウェルビーイングの考え方に繋がることもあり、SDGsへの取り組みの一環として注目が集まっています。
ウェルビーイングにおける3つの側面
ここでは、ウェルビーイングが持つ側面を3つ解説します。
医学的ウェルビーイング
医学的ウェルビーイングでは、心身がともに健康的な状態であるかどうかをチェックします。具体的には、健康診断やメンタルヘルスに関する質問紙などで測定します。
快楽主義的ウェルビーイング
快楽主義的ウェルビーイングは、気分といった精神的・感情的な状態に関する領域を表しています。表情や心拍、ホルモンなどの生理指標から計測が可能です。
持続的ウェルビーイング
持続的ウェルビーイングは、心身ともに自身の総合的な能力を発揮できる、意義ややりがいを感じているなど、気力に満ちて前向きな状態を指しています。近年は、持続的な観点から自分の状態を捉えていく考え方が主流になっているようです。
ギャラップ社によるウェルビーイングの考え方
ここでは、米国のコンサルティング企業であるギャラップ社によるウェルビーイングの考え方について解説します。ギャラップ社は、ウェルビーイングを構成する要素として、以下の5つを挙げています。
Career Well-being(キャリア・ウェルビーイング)
Career well-being(キャリア・ウェルビーイング)とは、1日の大半を占める活動に情熱を持って取り組んでいる状態です。仕事が中心となりますが、それに限らず、勉強・家事・育児といった私生活の活動も含まれます。
Social Well-being(ソーシャル・ウェルビーイング)
Social well-being(ソーシャル・ウェルビーイング)とは、人間関係に満足している状態です。具体的な例としては、周囲の人たちと信頼や愛情でつながっているといった状態が挙げられます。
Financial Well-being(ファイナンシャル・ウェルビーイング)
Financial well-being(ファイナンシャル・ウェルビーイング)とは、経済的に満たされている状態を指します。この概念について、アメリカの米消費者金融保護局(CFPB)は、「現在および継続的に経済的義務を果たすことができ、経済的安心を将来的にも感じられ、人生を楽しむための選択ができる状態である」と定義しています。
Physical Well-being(フィジカル・ウェルビーイング)
Physical well-being(フィジカル・ウェルビーイング)とは、心身共に健康であり、生活していく気力や体力が十分にある状態です。この概念のなかには、意欲的に仕事に取り組めるモチベーションを持っている状態も含まれます。
Community Well-being(コミュニティ・ウェルビーイング)
Community well-being(コミュニティ・ウェルビーイング)とは、自身を取り巻くコミュニティが充実している状態を指しています。コミュニティの例はさまざまで、職場や地域社会などが該当します。
PERMA理論によるウェルビーイングの考え方
ここでは、PERMA理論によるウェルビーイングの考え方について解説します。この理論は、マーティン・セリグマン博士によって2011年に発表されました。人が持続的な幸福を感じるためには、以下で紹介する5つの要素を満たす必要があるとしています。
Positive Emotion(ポジティブ・エモーション)
Positive Emotion(ポジティブ・エモーション)とは、日常から感じる肯定的な感情(ポジティブ感情)のことです。肯定的な感情の例としては、愛・感謝・喜び・思いやり・興味などが挙げられます。
Engagement(エンゲージメント)
Engagement(エンゲージメント)とは、時間を忘れて物事に没頭したり夢中になったりする状態のことです。ある活動に対して高い集中力を発揮する「フロー理論」の概念と、一致する考えとされています。
Relationship(リレーションシップ)
Relationship(リレーションシップ)とは、家族、パートナー、友人、上司、部下など、社会における幅広い人間関係のことです。他者との関わりは人生の幸福度と満足度を高めるとされています。
Meaning(ミーニング)
Meaning(ミーニング)とは、人生の意味や意義を指しています。何に価値を見出すか、何を大切にするのか、何を優先するのか、などが例として挙げられます。
Accomplishment(アコンプリシュメント)
Accomplishment(アコンプリシュメント)とは、自身で設定した目標や夢を努力して達成することです。目標に対する努力・達成が、幸福度向上につながります。
企業がウェルビーイング経営に取り組むメリット
ここでは、企業がウェルビーイングの概念を取りいれたウェルビーイング経営に取り組むメリットについて解説します。
生産性が向上する
ウェルビーイングを意識した経営・施策に取り組むことで、従業員の仕事に対するやりがいや働きやすさを向上させることができます。モチベーションを維持しつつ、主体的に業務に取り組むようになり、結果的に会社全体の生産性が上がります。
離職率が低下する
従業員の主な離職理由の1つに、職場内の人間関係が悪いことが挙げられます。ウェルビーイングをはかる指標である、PERMA理論における「Relationship」やギャラップ社のCommunity well-being」の考えを取り入れて職場環境の改善に取り組むことで、離職率低下を期待することができるでしょう。
ウェルビーイング経営を実践するための方法
以下では、ウェルビーイング経営を実践するための方法について解説します。
労働環境を見直す
長時間労働の是正や休暇制度の見直しといった労働環境の改善に取り組むと、ウェルビーイングが向上します。働き方に関する従業員の考えも多様化しているため、ニーズにあわせた労働環境を整えることで、ウェルビーイングを高められるでしょう。
社内コミュニケーションを活性化させる
社内のチームワークやコミュニケーションが良好で風通しの良い人間関係を構築であれば、ウェルビーイングは高まります。上司と部下のコミュニケーションの活性化や、コミュニケーションツールの導入などが検討できるでしょう。
福利厚生を充実させる
従業員のウェルビーイングを向上させるためには、福利厚生制度の充実も効果的です。具体的な例としては、食事や家賃の補助、健康維持のための定期的な人間ドックの受診支援などが考えられます。近年では「Financial Well-being」(お金の健康度)に着目した、従業員の金融リテラシー向上・資産形成支援に関する取り組みも注目が高まっています。
ウェルビーイング概念を取り入れる際の注意点
企業経営にウェルビーイングの考え方を取り入れる際の注意点は、以下のとおりです。
・成果を数値化する
・中長期的に取り組む
取り組みの効果を客観的に評価するためには、定量的な測定が可能な施策に取り組むことが重要です。従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイといった調査手法を用いて、意図した効果が得られているかを定量的に測定することを心がけましょう。
また、中長期的な目線で施策に取り組むことも意識しましょう。ウェルビーイングの向上は、短期的な取り組みでは成果が出ないものも多くあります。期待する効果や施策の性質を見極めた上で取り組みましょう。
ウェルビーイング概念を経営に取り入れた事例
ここでは、ウェルビーイング概念を経営に取り入れた事例について解説します。
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社は、すべての従業員が「より充実した・不安のない」人生を送れる体制を整えています。福利厚生やダイバーシティ、職場環境、人材育成の各方面から従業員をサポートしており、充実した環境で活躍できるよう配慮を行き届かせています。
ロート製薬株式会社
ロート製薬株式会社は、健康・コミュニケーション・挑戦に向けた取り組みを実施しています。同社は、健康社内通貨「ARUCO」を導入しています。歩行といった指定の活動を行うことでARUCOコインが貯まり、貯めたコインを使うことで、従業員はヘルシーランチの提供をはじめとするさまざまな恩恵に預かれます。
イケア・ジャパン株式会社
イケア・ジャパン株式会社は、従業員割引や食事補助に加え、事業所内保育施設、オンライン学習ツールの無料提供などで、働きやすさと満足度を向上しています。同社は、民間の福利厚生表彰・認証制度「ハタラクエール」を取得しており、その取り組みは対外的にも認められています。
まとめ
従業員のことを大切にする環境を整えたいなら、ウェルビーイングの考え方を経営に取り入れましょう。従業員のウェルビーイング向上に取り組むことで、従業員は高いモチベーションを維持しながら働けます。
ウェルビーイング向上の一環として、「Financial Well-being」(お金の健康度)に着目した施策に取り組むことも効果的です。オンアドでは「従業員のお金の悩み解決」によってウェルビーイング向上をサポートする「お金の福利厚生サービス」を提供しています。金融教育動画コンテンツやウェブセミナー、資産管理アプリやライフプランニングを中心とした従業員向け個別相談サービスにより、企業成長をサポ―トします。ご関心をお持ちの方はお気軽にお問合せください。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。