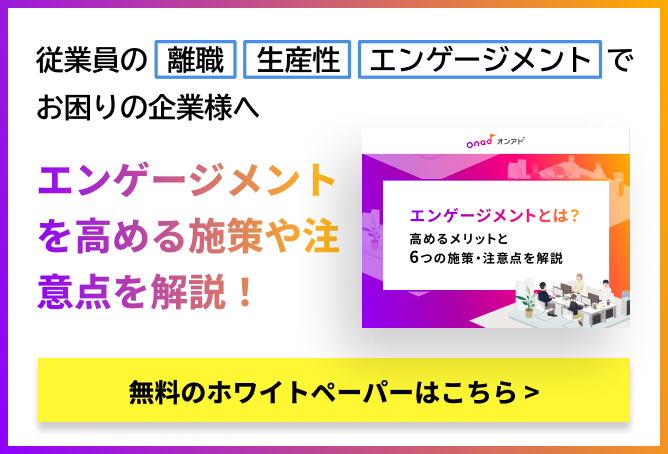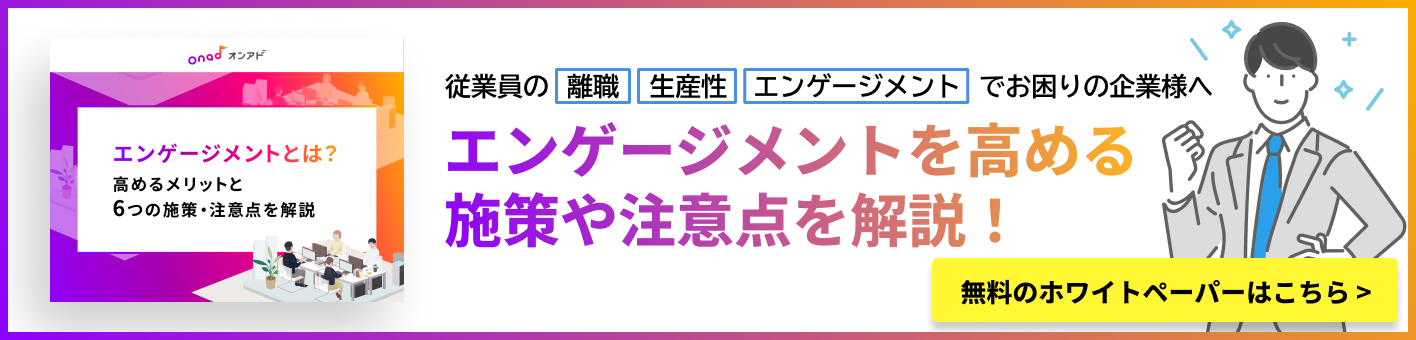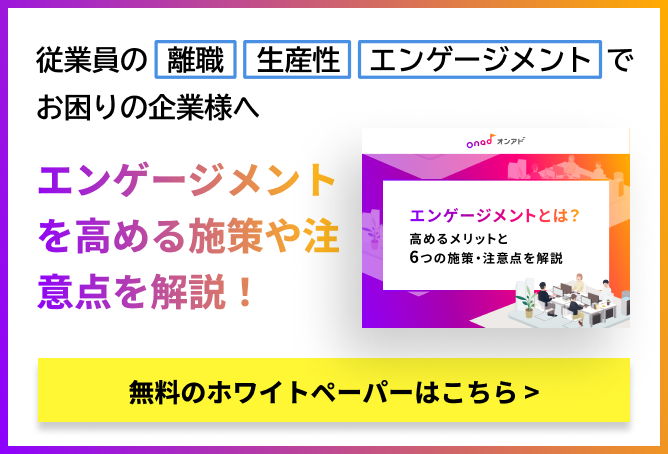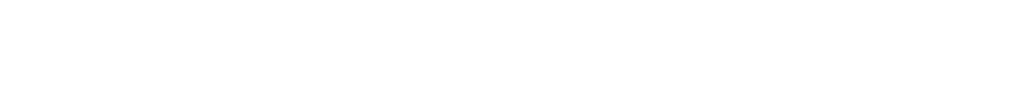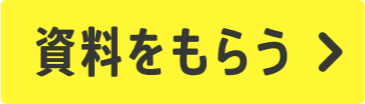SHARE
SHARE
生産性向上とは?業務効率化との違いや効果的な施策、メリットを解説
生産性向上 |
生産性向上に向けた取り組みには、指標や種類、施策が多数あるため、何から始めて良いかわからず頭を抱えている人もいるでしょう。
本記事では、生産性を効果的に向上させるポイントや注意点、生産性向上のメリットなどを解説します。どこから着手すべきか迷っている人は、参考にしてください。
目次
生産性向上とは
生産性向上とは、具体的にどのような内容を指すのでしょうか。ここでは、生産性向上の意味や似た言葉との違いについて解説します。
生産性向上の意味
生産性とは、インプットに対して得られたアウトプットの割合のことです。インプットとは、投資資源であるヒト・モノ・カネ・情報などを指します。対してアウトプットとは、生産物である成果や価値などのことです。生産性向上とは、少ないインプットで、アウトプット多く生み出すことを指します。限られた資源をうまく利用し、成果を上げることが大切です。
業務効率化との違い
生産性向上と似た言葉に業務効率化があります。業務効率化は「ムリ」「ムラ」「ムダ」のある業務内容を効率化し、業務の「改善」に向けて取り組むことです。生産性向上では「成果」の最大化が重視される一方で、業務効率化は業務に不必要な、無駄や無理を減らす取り組みといえるでしょう。
生産性向上が重要な理由
近年、ビジネスの現場で生産性向上が重要視されているのはなぜでしょうか。ここでは、生産性向上が重要な理由を解説します。
少子高齢化による人口減少
少子高齢化が加速している日本では、将来的に少子高齢化による労働力人口(15~64歳)の減少が続くと予測されています。労働力人口減少の影響による人材不足を懸念する声は高まっていますが、雇用者を増やすことは容易ではないため、個人の生産性を上げていく必要があります。
日本企業の国際的な労働競争力の低下
日本生産性本部によると、日本の1人当たりの労働生産性は、OECD加盟38か国中31位と、1970年以降で最も低い水準です。そのため、今後日本企業がグローバル市場で勝ち残るためには、限られた資源で価値の高い成果を生み出していく必要があります。
働き方改革やワークライフバランスの推進
2019年より労働生産性の向上をねらい、「働き方改革」に関連する法律が施行されました。これにより、ワークライフバランスの推進など、働きやすい環境の整備が求められるようになりました。従業員の心身の健康に配慮しつつ、生産性を維持向上する取り組みが必要となっています。
生産性の種類
生産性には、さまざまな種類があります。以下で、それぞれについて詳しく解説します。
付加価値労働生産性
「付加価値額」とは、売り上げから諸経費を差し引いた「粗利」のことです。付加価値労働生産性は、付加価値額÷労働量で算出できます。同じ労働時間と人員を維持しながら、売上高の増加や原材料費の削減などを行い、付加価値額を高めることが可能です。
物的労働生産性
物的労働生産性とは、生産量や個数など、目に見えるものを測る指標のことです。生産量を労働者数や労働時間で割ったときの比率で、従業員1人あたりの労働時間に対し、平均して生産できる製品の個数を示します。物的労働生産性を上げるには、製造工程や製造方法の見直しが必要です。
全要素生産性(TFP)
全要素生産性(TFP)とは、労働や資本、原材料に限らず、生産性に関わる全要素を考慮して算出されるものです。生産性に関わる要素のなかには、技術の進歩なども含まれます。投下費用に対して、どれだけの付加価値が発生したかを算出できます。
生産性向上の施策
生産性向上の施策を考えるためには、指標が必要です。以下では、施策を決めるために参考になる型を解説します。組織や業務内容に即した方法を検討するために、ぜひ役立ててください。
h3:インプット縮小型
「インプット縮小型」とは、アウトプット(付加価値)や生産量は維持したまま、投入するインプット(資源)を減らすための施策のことです。
事業の統廃合やリストラをはじめとする、不採算部門の縮小といったより積極的な施策は「インプット大幅縮小型」施策と呼ばれています。
アウトプット拡大型
「アウトプット拡大型」とは、インプット(資源)は維持しながら、アウトプット(付加価値)を増やす施策のことです。労働時間あたりの成果を最大化させるために、システムやITツールの導入、従業員研修などを実施します。
生産性が高い事業への集中投資を行うといったより積極的な施策は「アウトプット大幅拡大型とも呼ばれています。
生産性向上で得られるメリット
生産性向上がもたらすメリットは、利益の増加だけではありません。以下では、生産性向上で得られるメリットについて詳しく解説します。
コスト削減につながる
生産性が向上すると、従業員の労働時間や原材料費を減らせます。そのため、人件費や原価のコスト削減にも期待することが可能です。また、削減できたコストを、労働環境の改善やサービスの付加価値向上など、別のことに使えるようになります。
ワークライフバランスの実現
生産性向上によって、従業員の残業時間や長時間労働が減少するため、ワークライフバランスの改善につながります。オンオフの切り替えができるようになったり、自分の時間が作れるようになったりすることで、従業員のモチベーションが高まり、結果的にパフォーマンスの向上にも期待できるでしょう。
h3:従業員満足度の向上につながる
生産性が向上すると業績が拡大し、給与をはじめとする各種待遇の改善ができるようになります。その結果、従業員の満足度が上がり、業務に対するモチベーションも向上するため、企業へのエンゲージメントも高まります。離職率の低下といった効果も期待できるでしょう。
h2:生産性向上に向けた効果的な方法
ここまで、生産性向上によって企業や従業員が得られるメリットについて解説しましたが、生産性を向上させるには、一体どのような方法があるのでしょうか。6つの項目を解説します。
現状分析や課題整理などの見える化
業務の改善を行うためには、「ムダ」な業務の洗い出しや業務の棚卸しが必要です。そのため、まずは業務の見える化に取り組みましょう。できれば従業員にも意見を募って、業務上の課題を細かく検証するとよいでしょう。現場の声に耳を傾けることで、実際の課題を見つけることが可能です。
業務の取捨選択によるスリム化
過剰なコストや「ムダ」な工程などの業務を洗い出したら、それらの業務をスリム化する方法を検討します。まとめられる複数の業務があるかどうかや、特定の従業員へ負担がかかっていないか、成果に「ムラ」がないかなどに、目を向けることが大切です。
アウトソーシングの検討
ノンコア業務が肥大化してしまい、コア業務にリソースが割けない状況であれば、ノンコア業務をアウトソーシングすることも、検討するとよいでしょう。アウトソーシングにより、社内でしか行えない業務に集中できるようになるほか、社内でノンコア業務の引き継ぎや指導の手間が不要になる点も、メリットといえます。
適切な人員の再配置とスキルアップ
適切な人員配置を行うためには、従業員が現在保有しているスキルや資格、業務経験をまとめ、必要に応じて人材を再配置します。また人材の計画的な育成も将来的な生産性向上につながります。中長期的な計画として、従業員のスキルアップを進めるための研修や対策を、継続的に取り入れましょう。
ITツールやテクノロジーの活用
業務を円滑に進めたり、効率よく進めたりするためには、ITツールやテクノロジーの活用も有用です。モバイル端末や情報共有を行うデジタルツールの活用、ペーパーレス化の導入を検討しましょう。なかでも、複雑な作業や業務を自動化できるRPA(Robotic Process Automation)は、最近注目されている技術です。
柔軟な働き方によるエンゲージメント向上
企業に対する愛着や、企業理念への共感を示す組織エンゲージメントが低いと、ミスの増加や生産性の低下につながる可能性があります。優秀な人材が離職するのを防ぐためにも、従業員へサーベイなどを活用した現状把握を実施し、従業員が誇りをもって働ける環境づくりに向けて、適切な施策を進めていく必要があります。
生産性向上に向けた取り組みにおける注意点
生産性向上のための取り組みは、無計画に進めると、かえって現場を混乱させてしまう可能性もあります。以下では、取り組みを適切に進めるための注意点を解説します。
マルチタスクや削減ばかりに取り組まない
「ムダ」を省きすぎるあまり、従業員が複数の業務を担当する「マルチタスク化」してしまうと、かえって作業効率を下げてしまう恐れがあります。そのため、別の知識やスキルを必要とする業務は、1人だけが抱えてしまわないように施策を考えなければいけません。
コスト・人員・労働力の削減ばかりに偏ることがないよう、どこを縮小・増大させるのかをバランスよく検討しましょう。
目的や目標を示す
「生産性」の定義は、業種や業態によって異なります。そのため、生産性が何を示すのかを明確化することも大切です。生産性の意味を明確化しておかないと、「生産性向上」にむけた取り組みも曖昧になってしまう恐れがあります。
組織が共通認識をもつには、生産性向上の定義や、なぜ生産性向上に取り組む必要があるのか目的を明確に示さなくてはいけません。同時に消費者視点に立ち、社会のニーズに沿っているかどうかも確認することが大切です。
繰り返しながら向上を進める
生産性向上の施策は、中長期的に取り組む必要があります。トライアルアンドエラーを繰り返すことを前提に、改善や調整をしながら繰り返し取り組むことが大切です。取り組み内容を検討するだけではなく、PDCA(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)を回す環境や仕組みも、考える必要があります。
生産性向上に活用できる助成金
生産性向上に取り組むにあたって、各省庁や各自治体による助成金制度も用意されています。助成金には、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「業務改善助成金」などがあります。このなかの「業務改善助成金」は、生産性向上のための設備投資をして賃金を一定額以上引き上げた場合に、費用の一部が助成される制度です。
h2:まとめ
生産性向上の取り組みは、企業の余分なコストの削減が行えるだけでなく、従業員満足度の改善などにも貢献します。従業員満足度が高い会社であれば、離職率も下がり、1人ひとりのパフォーマンスも向上するでしょう。
生産性向上にご関心をお持ちの方は、株式会社オンアドにぜひお問い合わせください。従業員の生産性が低下する要因である「お金の悩み」の解決を通じて、企業の生産性向上をサポートいたします。オンアドが提供する「お金の福利厚生サービス」にご関心があれば、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。