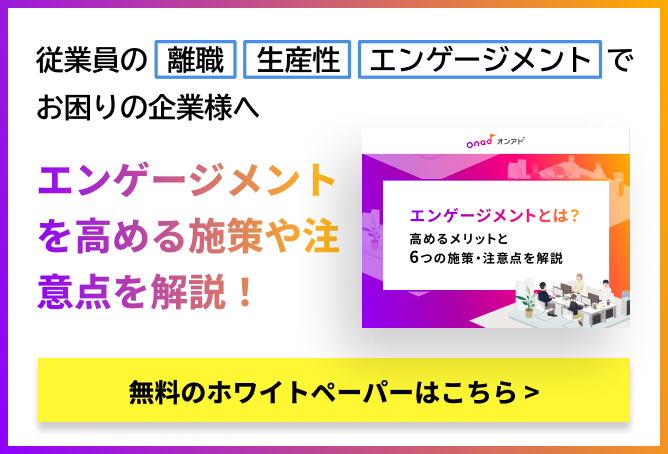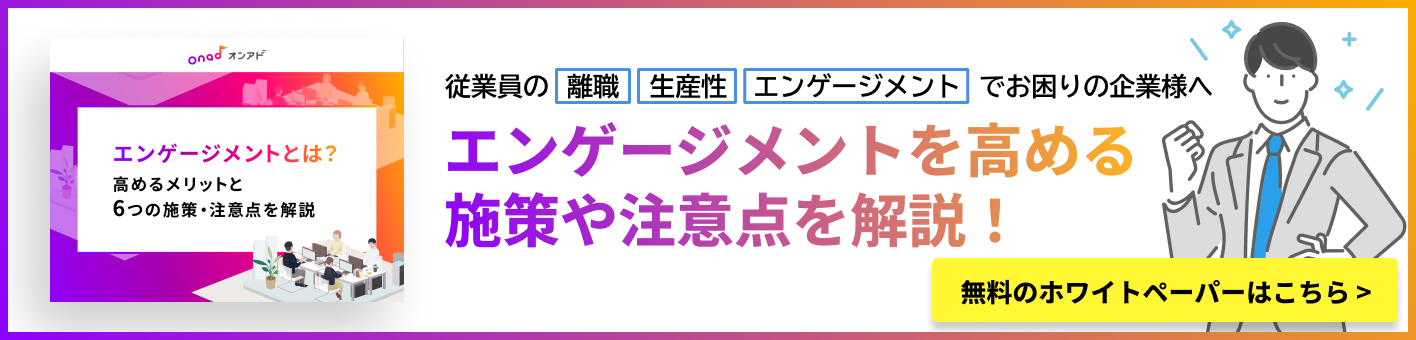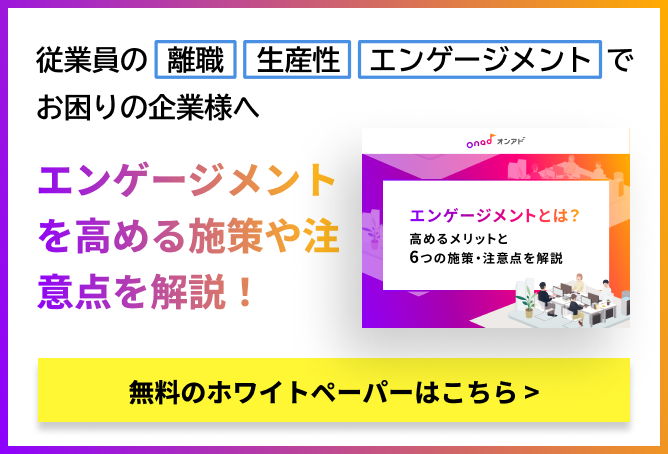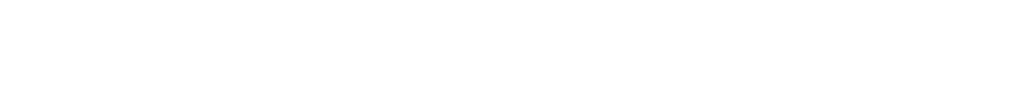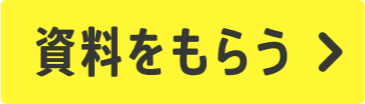SHARE
SHARE
「伊藤レポート」は人的資本経営に取り組むうえで重要な資料!具体的な内容を紹介
人的資本経営 |
近年、「人的資本経営」への注目はますます高まっています。これからの企業経営にとって、人的資本経営は欠かせない要素になりつつあるでしょう。
人的資本経営に取り組む際、参考にしたい資料が「伊藤レポート」です。本記事では、伊藤レポートとはどのような資料なのか、概要や特徴をわかりやすく解説します。
目次
人的資本経営とは
人的資本経営とは、人材(=働く従業員)を資本と考え、その価値を最大化することを目指す経営手法のことです。経営における従来の考え方では、人材を消費する「資源」とみなす側面が強くありました。一方で、人的資本経営では、人材を投資対象である「資本」と定義し、将来に渡って価値を生み出すものと捉えます。
「伊藤レポート」とは
「伊藤レポート」は、人的資本経営に関するトピックにおいて、頻繁に名前が挙がる資料の1つです。では、伊藤レポートとは一体どのような資料なのでしょうか。以下で詳しく解説します。
経済産業省によるプロジェクトの報告書
伊藤レポートは、経済産業省が実施したプロジェクトの報告書の通称です。同プロジェクトは、企業と投資家が良好な関係を築き、国際的な競争力を高めることを目的としており、「伊藤」という名称は、プロジェクトの座長である一橋大学名誉教授の伊藤邦雄氏に由来します。
伊藤レポートには、企業と投資家の関係構築における提言がまとめられているのが特徴で、2014年にはじめて公表されると、大きな反響を呼びました。
6つの基本メッセージ
伊藤レポートには、6つの基本メッセージが記載されています。内容は、以下のとおりです。
- 持続的成長の障害となる慣習やレガシーとの決別を
- イノベーション創出と高収益性を同時実現するモデル国家を
- 企業と投資家の「協創」による持続的価値創造を
- 資本コストを上回るROEを、そして資本効率革命を
- 企業と投資家による「高質の対話」を追求する「対話先進国」へ
- 全体最適に立ったインベストメント・チェーン変革を
引用:「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト(伊藤レポート) 最終報告書|経済産業省
「伊藤レポート」が公表された背景
伊藤レポートが公表された背景には、国内企業の収益性の低迷があります。日本国内の企業は高いポテンシャルを持つにもかかわらず、競争力が低下傾向にあります。伊藤レポートは、企業が継続的に成長し、競争力を高めるための指標となりえる報告書であるといえるでしょう。
これまで公表されてきた「伊藤レポート」
2014年の公表以来、伊藤レポートはさまざまなバージョンが作成されています。
2024年時点で公表されている資料は、以下の5つです。
- 伊藤レポート
- 伊藤レポート2.0
- 人材版伊藤レポート
- 人材版伊藤レポート2.0
- 伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)
それぞれのバージョンについて、以下で詳しく解説します。
伊藤レポート
初版の伊藤レポートは、2014年8月にはじめて公表された報告書です。初版の伊藤レポートは、国内のみならず海外からも大きな反響を呼びました。
伊藤レポート2.0
伊藤レポート2.0は、2017年10月に公表されたバージョンです。2014年に公表された初版の伊藤レポートをアップデートし、戦略投資のやり方や評価方法などに関する記載が追加されました。
人材版伊藤レポート
人材版伊藤レポートとは、2020年9月に公表された報告書で、それまでのレポートとは異なり、人的資本や組織体系にフォーカスした内容となっています。人材戦略において重要な視点と、共通要素がまとめられているのがポイントです。
人材版伊藤レポート2.0
人材版伊藤レポート2.0は、2022年5月に公表されたバージョンです。2020年の人材版伊藤レポートの改訂版であり、事例集が追加されたことで、より実践的な内容にまとめられています。
伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)
2022年8月に公表された伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)は、2024年5月時点で最新のバージョンです。伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)では、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の実現に向けた取り組みをまとめており、「サステナビリティへの取り組みが、企業価値の向上につながる」という考えのもと、作成された資料です。
人的資本経営において参照すべきは「人材版伊藤レポート」
伊藤レポートは、2014年の公表以来さまざまなバージョンが公表されてきました。そのなかでも、人的資本経営という概念が広まるきっかけとなったのは、2020年の「人材版伊藤レポート」です。前述のとおり、人材版伊藤レポートは人的資本に特化しています。
人的資本経営を実践するなら、まずは「人材版伊藤レポート」や、同レポートのアップデート版である「人材版伊藤レポート2.0」を参照するとよいでしょう。人材版伊藤レポート2.0は、旧版の内容を改定してつくられています。そのため、基本的な考え方はそのままに、具体的な取り組みやポイントについて触れられているのが特徴です。
「人材版伊藤レポート」における3つの視点
人材版伊藤レポートは、次の3つの視点で構成されます。
- 経営戦略と人材戦略の連動
- As is‐To be ギャップの定量把握
- 企業文化の定着
以下で、それぞれの視点のポイントについて詳しく解説します。
1.経営戦略と人材戦略の連動
経営戦略と人材戦略の連動は、人材版伊藤レポートのなかで最も重視されている視点です。両者には密接なかかわりがあるとされており、企業価値を向上させるためには、経営戦略の実現につながる人材戦略を実行することが大切です。企業は、各社に共通する要素や視点を取り入れつつも、自社の経営戦略にマッチした人材戦略を策定する必要があります。
2.As is‐To be ギャップの定量把握
人材戦略が経営戦略と連動しているか判断するためには、「As is(現在の姿)」と「To be(目指すべき姿)」の差を把握し、ギャップを埋める取り組みを行うことが重要です。実行段階においては、人材面における課題ごとに、KPIを設定してPDCAサイクルを回しましょう。
3.企業文化の定着
人的資本経営を企業文化として定着させることが、企業の持続的な成長につながります。経営トップ自らが率先して取り組み、企業文化の定着を図りましょう。また、必要に応じて企業理念や存在意義を見直し、最適化することも重要です。
「人材版伊藤レポート」における5つの共通要素
人材版伊藤レポートでは、人的資本経営における5つの共通要素が示されています。以下で、5つの共通要素について詳しく解説します。
1.動的な人材ポートフォリオ
動的な人材ポートフォリオとは、企業の成長戦略を考えたときに、必要な人材をタイプごとに分けて分析したものです。将来的な目標から逆算して、必要な人材の要件を定義します。動的な人材ポートフォリオには、文字どおり動的な管理が求められます。
2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
中長期的な企業価値向上には、イノベーションの創出が不可欠です。そのためには、価値観や専門性などの知と経験の多様性を実現し、取り込む必要があります。従業員の多彩な経験やスキルの多様性を認め、受容する「ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包括・受容)」を実現することが大切です。
3.リスキル・学び直し
事業環境の変化や価値観の多様化に対応するためには、従業員のリスキルや学び直しを促進し、経営戦略実現に向けたスキルを身に付けてもらうことが大切です。たとえば、学習機会や教育プログラムの提供といった取り組みなどが挙げられます。
4.従業員エンゲージメント
エンゲージメントが向上すれば、従業員は高いモチベーションを持ち、自発的に業務に取り組めるようになります。従業員エンゲージメントを向上させることは、企業の経営戦略の実現につながりやすい環境を整えることにもつながるでしょう。従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員が仕事に価値ややりがいを感じられるような環境を整えることが重要です。
5.時間や場所にとらわれない働き方
近年は、従業員のライフスタイルや個人の事情に合わせた、柔軟な働き方を設定することが重視されています。たとえば、リモートワークやフレックスタイム制を取り入れるなどの施策が考えられます。これらの制度を取り入れつつ、業務プロセスの見直しや、円滑なコミュニケーションを保つ施策も必要です。
企業経営の関係者に求められる役割・行動
人的資本経営を実現するためには、ステークホルダーがそれぞれの役割を理解し、行動することが重要です。以下では、伊藤レポートで示されている経営陣・取締役会・投資家の役割・行動について解説します。
経営陣に求められる役割・行動
まず、経営陣には以下のような役割や行動が求められます。
- 企業の理念や存在意義(パーパス)、経営戦略の明確化
- 経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行
- CHROの設置・選任、経営トップ5Cの密接な連携
- 従業員・投資家への積極的な発信・対話
取締役会に求められる役割・行動
次に、取締役会に求められる役割や行動は、以下のとおりです。
- 人材戦略に関する取締役会の役割明確化
- 人材戦略に関する監督・モニタリング
投資家に求められる役割・行動
最後に、投資家には以下の役割や行動が求められます。
- 中長期的視点からの建設的対話
- 企業価値向上につながる人材戦略の「見える化」を踏まえた対話、投資先の選定
人的資本経営を実践する3つのステップ
それでは、人的資本経営を実際に実践するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。人的資本経営を実践するためには、次の3つのステップが必要です。
STEP1.目指すべき姿やビジョンの設定
STEP2.KPIの設定・施策の立案
STEP3.施策実行・効果検証
それぞれの工程について、以下で詳しく解説します。
STEP1.目指すべき姿やビジョンの設定
まず、人的資本経営を実践するためには、自社の現状を客観的に整理することが大切です。経営戦略と人材戦略を紐づけ、自社が目指すべき姿やビジョンを設定しましょう。
STEP2.KPIの設定・施策の立案
次に、自社にとって必要な人材を明確化し、現状と理想のギャップを把握します。続いて、このギャップを埋めるための具体的な施策を検討することも大切です。必須ではありませんが、施策に対して定量的なKPIを設定することで、より具体的に明確化できます。
STEP3.施策実行・効果検証
STEP2で策定した施策を実施したら、その効果を検証します。効果検証の方法としては、人事データの整理やエンゲージメントサーベイなどが挙げられます。施策の効果と課題を見極め、PDCAサイクルを回していきましょう。
まとめ
伊藤レポートとは、経済産業省のプロジェクトの報告書の通称で、これまでさまざまなバージョンが登場しています。そのなかでも、人的資本経営の実現におけるバイブルとされている報告書が「人材版伊藤レポート」です。報告書の内容は自由に閲覧できるため、人的資本経営に取り組む予定の企業は、ぜひ一度目を通してみるとよいでしょう。
人的資本経営を実現するためには、従業員エンゲージメントを向上させる必要があります。エンゲージメントを向上させるにあたって、「ファイナンシャル・ウェルネス向上」も効果的な取り組みの1つです。オンアドは従業員の「お金の悩み解決」を通じて人的資本経営の実現をサポートする「お金の福利厚生サービス」を提供しています。ご関心をお持ちの方は、ぜひお問合せ下さい。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。