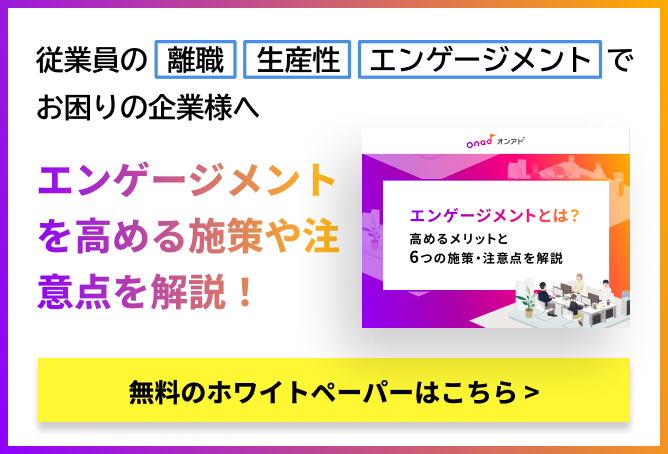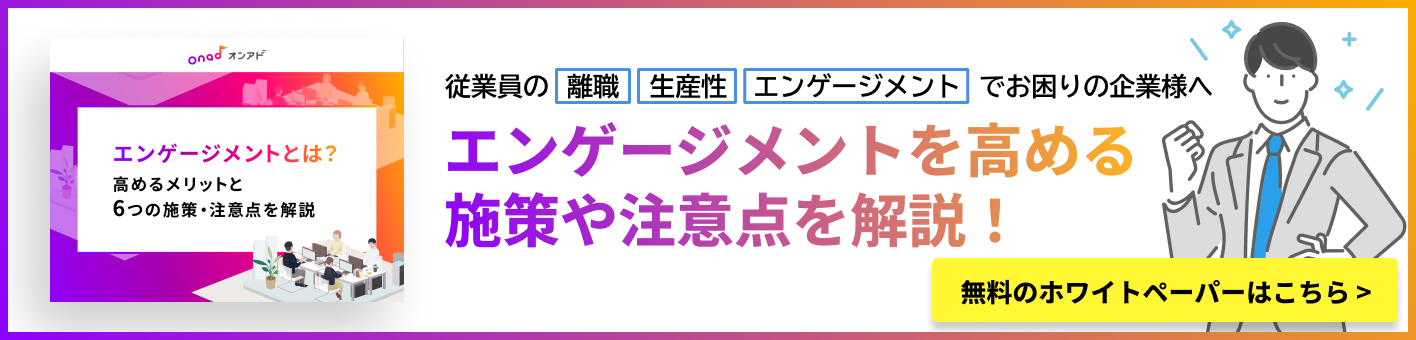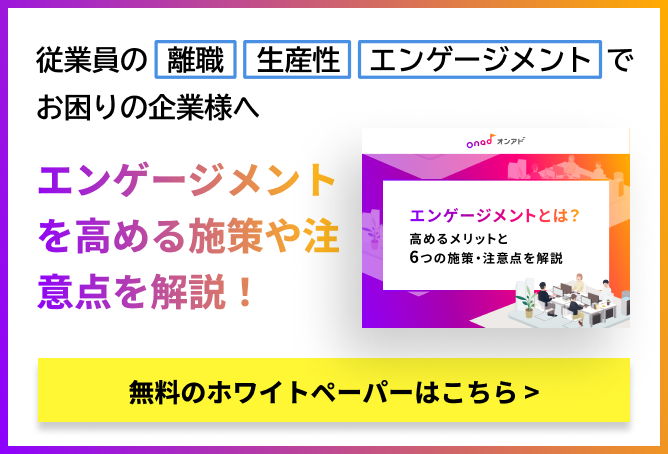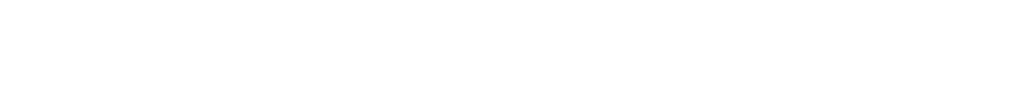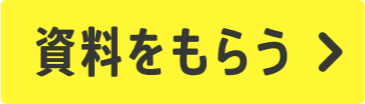SHARE
SHARE
人的資本経営と健康経営の関連性とは|具体的な施策や成功のポイントも解説
人的資本経営 |
近年、人的資本経営への注目度はますます高まっています。人的資本経営を推進するためには、健康経営に取り組むことが重要です。 では、両者には具体的にどのような関わりがあるのでしょうか。本記事では、人的資本経営と健康経営の関連性について詳しく解説します。健康経営の具体的な取り組み例も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
人的資本経営・健康経営の概要
人的資本経営の推進には、健康経営への取り組みが欠かせません。ここではまず、人的資本経営と健康経営の概要について解説します。
人的資本経営
人的資本経営とは、自社の従業員(=人材)を資本として捉える考え方です。個々が持つ力を最大限に引き出し、自社の成長につなげます。これまでの経営戦略では、人材を消費する「資源」として捉える考え方が一般的でした。一方、人的資本経営では、人材を投資すべき「資本」と捉えて、積極的な人材戦略を実行します。
健康経営
健康経営とは、従業員の健康管理や、労働環境の改善に積極的に取り組み、自社の成長につなげる経営手法です。ワークライフバランスが推進されるなか、日本でも健康経営の注目度が高まっていきました。
人的資本経営と健康経営の関連性とは
人的資本経営では人材=資産として扱うため、従業員の健康管理は、人的資本経営を実現する基盤と考えられます。実際に、人的資本経営のガイドラインとして広く活用されている「伊藤レポート」でも、健康経営についての言及がなされています。人的資本経営を実践するなら、健康経営には欠かさず取り組むことが重要です。
人的資本の情報開示における健康指標
2023年3月決算以降、上場企業を中心とした大企業4,000社に対して、人的資本の情報開示が義務化されました。情報開示は、企業イメージの向上や従業員のモチベーションアップにつながります。健康指標の情報において、現状開示義務はありませんが、今後対象になる可能性は十分あるでしょう。
健康指標の代表的な項目としては、次の5つがあります。
・労働災害の関連指標
・離職率
・労働時間
・健康診断受診率
・ストレスチェック受検率
人的資本経営に取り組むメリット
人的資本経営に取り組むと、主に3つのメリットが期待できます。
・適切な人材配置が可能となる
・エンゲージメントや生産性の向上につながる
・人材が集まりやすくなる
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
適切な人材配置が可能となる
人的資本経営に取り組めば、個々の従業員のスキルや能力を把握できるようになり、適切な人材配置が可能となります。その人本来の実力を発揮できるようになるため、個々がより高い成果を発揮することが可能です。また、人的資本経営は、自社に不足している人材の見極めにも役立ち、研修や育成制度の改善にもつながります。
エンゲージメントや生産性の向上につながる
人材を大切な資本として扱い、人材育成に力を入れる姿勢は、従業員にも伝わるものです。そのため、人的資本経営に取り組むことによって、従業員のエンゲージメントや仕事へのモチベーションも向上する可能性が高まります。従業員の会社に対する貢献意欲が高まることで、生産性の向上にもつながるでしょう。
人材が集まりやすくなる
人的資本経営に取り組んでいることは、求職者へのアピールポイントにもなります。人的資本経営への取り組みは、企業イメージの向上にも寄与するため、結果的に優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。
健康経営の具体的な取り組み例
ここからは、健康経営の取り組みについてさらに詳しく解説します。具体的には、次のような施策の実施がおすすめです。
・健康診断の実施・受診率の向上
・ワークライフバランスの実現支援
・社内コミュニケーションの促進
・食生活の改善・運動促進
・治療と仕事の両立サポート
それぞれの取り組みについて、以下で詳しく解説します。
健康診断の実施・受診率の向上
健康診断の実施は、企業に課せられた義務の1つです。しかし、事業規模が小さくなるほど、健康診断の実施率は下がる傾向があります。また、実施はしていても受診率が100%でないケースも少なくありません。
そのため、未受診者への声かけや通知など、受診率をアップさせる取り組みも並行して行うとよいでしょう。また、診断結果に応じて、再検査や特定保健指導が必要な従業員に、受診を促すことも大切です。
ワークライフバランスの実現を支援
従業員が、仕事とプライベートを両立できるような体制を整えることも重要です。たとえば、テレワークやフレックスタイム制の導入や、有給休暇の取得推進、ノー残業デーの設定などが考えられます。
社内コミュニケーションの促進
社内コミュニケーションを促進することで、風通しのよい職場環境をつくりましょう。従業員の心理的安全性が保たれ、結果的に従業員のメンタルヘルスにポジティブな影響をもたらします。
食生活の改善・運動促進
健康状態に直結する「食事」と「運動」に着目し、従業員の健康をサポートすることも大切です。たとえば、健康に配慮した食事の提供・金銭補助や、スポーツクラブとの提携などの施策が挙げられます。
治療と仕事の両立サポート
従業員が病気になっても、治療と仕事を無理なく両立できるようなサポート体制を整えましょう。「病気になっても働ける環境づくり」は、定年年齢の引き上げにより高齢人材が増えるにつれ、さらに重要なテーマになっていくと考えられます。
健康経営を成功させるポイント
健康経営を成功させるためには、次の3つのポイントを押さえることが肝心です。
・従業員の健康意識を高める
・健康経営のゴールを明確化する
・従業員のニーズを把握する
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
従業員の健康意識を高める
健康経営を成功させるためには、従業員の健康意識を高める必要があります。そのため、健康経営の施策における目的や意味を周知することが大切です。楽しく取り組める社内イベントを開催して、従業員を自然に巻き込んだり、セミナーを実施したりするなどして、健康に意識を向けてもらいましょう。
健康経営のゴールを明確化する
経営側と従業員側が、同じ目標を共有できるよう、健康経営のゴールを明確化することも重要です。その際、漠然とした表現ではなく、数値化した目標を設定しましょう。
従業員のニーズを把握する
経営側のニーズに基づく施策ばかり実施すると、従業員に「押し付けられている」という感覚を与えてしまい、反感を買う恐れがあります。そのため、きちんと従業員のニーズを把握したうえで、的確な施策を検討しましょう。
健康経営における代表的な認定制度
健康経営に取り組んでいる証として、認定制度の取得を目指すこともおすすめです。
ここでは、健康経営における代表的な認定制度を紹介します。
1.健康経営優良法人
健康経営優良法人は、健康経営に取り組む企業を認定する公的制度です。大規模法人部門と中小規模法人部門に分かれており、認定された企業は、PRとして「健康経営優良法人のロゴマーク」を使用できるようになります。自治体や金融機関において、インセンティブを受けられる点もメリットの1つです。
2.健康宣言事業
健康宣言事業は、協会けんぽや健康保険組合による制度です。(正式な名称は、自社が加入している保険者により異なります)健康保険加入者の健康増進を目的に、健康宣言をした企業を支援する制度で、健康経営に取り組むうえでのサポートやアドバイスも受けられます。保険者と連携しながら、従業員やその家族の健康を守るための取り組みを、実施することが可能です。
3.健康経営銘柄
健康経営銘柄は、健康経営に取り組む上場企業を対象とした制度です。東京証券取引所と経済産業省が、優れた取り組みを実施する企業を認定します。健康経営銘柄に認定されれば、企業としての魅力を投資家にアピールできるでしょう。上場している必要があるため、認定のハードルは高いといえますが、長期的な目標としては有用です。
※参照:健康経営銘柄|経済産業省
まとめ
人的資本経営を実現するためには、大切な資産である従業員の健康を管理することも重要です。健康診断の実施はもちろんのこと、社内コミュニケーションの促進など多角的な施策を実施し、従業員が健康でいきいきと働ける環境を整えましょう。 人的資本経営を実践するなら、健康経営と並行して「ファイナンシャル・ウェルネス」に取り組むこともおすすめです。従業員の「お金の不安」が解消されれば、自社で安心して長く働いてもらうことができるでしょう。オンアドの「お金に福利厚生サービス」にご関心をお持ちの方は、是非お問合せください。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。