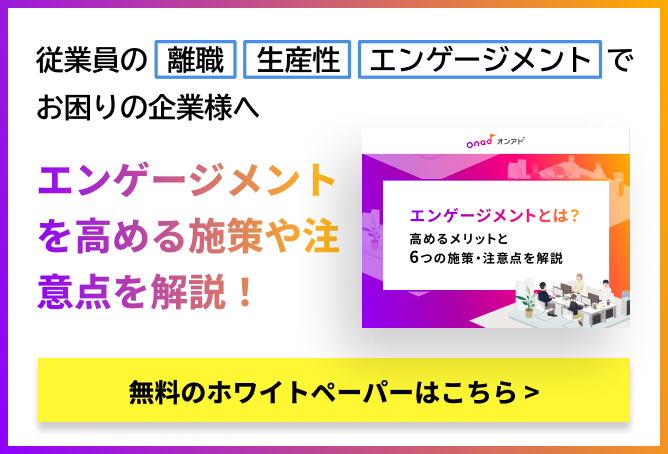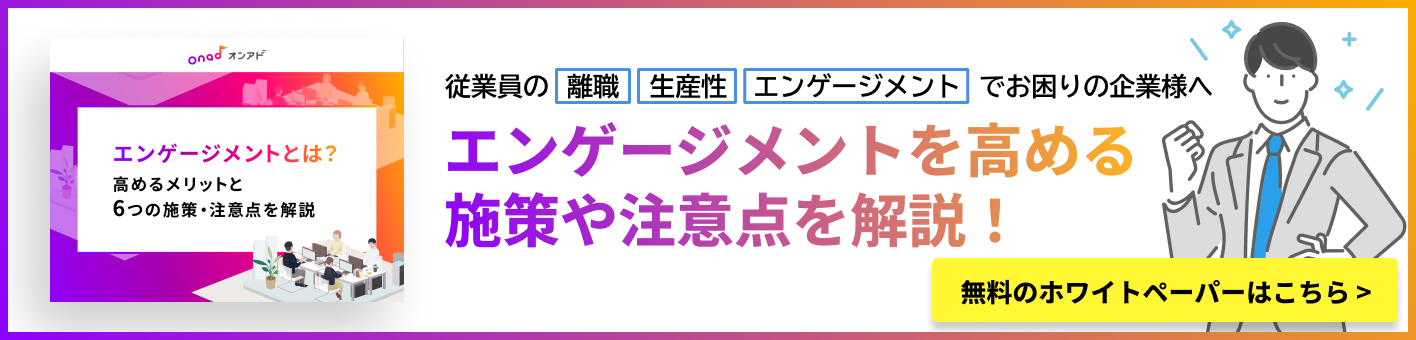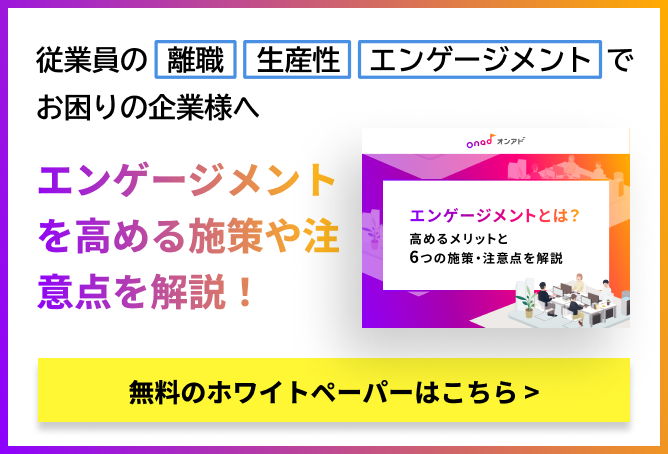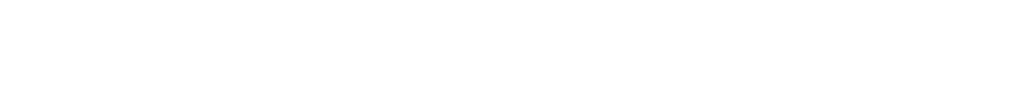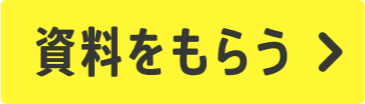SHARE
SHARE
帰属意識とは?エンゲージメントとの違いや高めるメリットを解説
エンゲージメント |
従業員の定着率を向上させるには、モチベーションを持って働ける環境の整備や、帰属意識を高める取り組みが重要です。
この記事では、帰属意識の概要や高めるメリット、帰属意識が低くなる原因を解説します。従業員の帰属意識を高めたい人は、参考にしてください。
目次
帰属意識とは
帰属意識とは、組織について自分がその一員であるという意識・感覚を指す言葉です。会社をはじめとして、さまざま単位の集団・組織に対して用いられます。帰属意識は、学術的には「組織コミットメント」と呼ばれています。
企業における帰属意識の重要性
従業員の帰属意識が高いと、その集団・組織との一体感を持ち、興味関心や愛着が強い状態になります。その分メンバーの士気が高まり、成果を上げやすくなるでしょう。この点からも、企業において帰属意識は重要な要素といえます。
帰属意識が注目されている背景
帰属意識が注目されている背景としては、さまざまな業界において人材の流動化が進んでいることが挙げられます。
昔のように終身雇用が当たり前だった時代と異なり、現在では転職が一般的となっているため、企業にたいする帰属意識を感じていない人も少なくありません。また、コロナ禍の影響によってリモートワークが普及していることも、企業に対する帰属意識が低下している要因の1つです。そのため、帰属意識をもたせることで人材の定着率を高めようとする動きが活発になっています。
帰属意識とエンゲージメントの違い
帰属意識と似た意味の言葉に、エンゲージメントがあります。エンゲージメントとは、深い関わり合いや関係性を指す言葉です。そのほかにも、以下のような意味を持ちます。
・婚約
・雇用
・従事
・誓約
など
以下では、エンゲージメントの種類について解説します。
従業員エンゲージメント
従業員エンゲージメントとは、従業員が自発的に「自社に貢献したい」と思う意欲を指す言葉です。また、従業員の企業に対する信頼の度合いなどを、示す言葉でもあります。ただし、従業員エンゲージメントという言葉は、複数の意味合いを持つのが特徴です。1つの意味合いを指す言葉ではなく、定義がシチュエーションや文脈によって異なる点も覚えておきましょう。
ワークエンゲージメント
ワークエンゲージメントとは、従業員の仕事に対する意欲やメンタル面における健康度を示す言葉です。具体的には、従業員の仕事に対する熱意や没頭、活力が満たされている状態を示しています。ワークエンゲージメントが充実していると、従業員は業務において高いパフォーマンスを発揮するでしょう。
帰属意識とロイヤルティの違い
エンゲージメントと同じく、帰属意識と似た言葉にロイヤルティがあります。ロイヤルティとは、従業員が企業に対して抱く忠誠心などを指す言葉です。帰属意識との相違点として、ロイヤルティは企業が上位で従業員が下位という力関係のもとで、成り立っている点が挙げられます。ロイヤルティは、企業と従業員の間に明確な力関係があることが前提です。
帰属意識を高めるメリット
ここでは、帰属意識を高めるメリットについて解説します。
モチベーションが向上する
帰属意識を高めるメリットとして、従業員のモチベーション向上が挙げられます。モチベーションが向上する理由は、帰属意識によって自分は企業に必要とされている人材だと認識でき、より企業に貢献したいとの思いが生まれるためです。モチベーションが向上することで、業績へのさらなる貢献も期待できるでしょう。
定着率が高まる
企業への定着率が高まる点も、帰属意識を高めるメリットの1つです。帰属意識が高まると、従業員の企業に対する愛社精神や働きがいが強化されます。結果的に離職率が低くなり、定着率が高まるのが利点です。そのため、自然と従業員の入れ替わりも少なくなります。
組織力が高まる
帰属意識を高めることで、グループ内でのチームワークが生まれやすくなり、組織力が向上します。モチベーションの上昇と同じく、組織力が高まることで、個々のパフォーマンスだけでなく、チームとしてのパフォーマンス向上も期待できます。結果的に生産性が高まり、業績がアップするでしょう。
帰属意識がないことによるデメリット
ここでは、帰属意識がないことによるデメリットを解説します。
生産性が低下する
帰属意識がないことによるデメリットは、生産性の低下です。従業員の帰属意識が低い場合、業務にたいするモチベーションや職場に貢献したいという貢献意識が低下するため、結果として生産性が低下してしまう恐れが出てきます。
コミュニケーションが薄くなる
社内のコミュニケーションが薄くなる点も、帰属意識がないことによるデメリットの1つです。従業員に帰属意識がないと、企業への関心が低下しやすくなります。そのような状態の従業員が増加することで、社内コミュニケーションが図りにくくなるでしょう。コミュニケーションが停滞することによって、経営陣が示す会社の理念や方針も浸透しにくくなります。
従業員の負担が増える
帰属意識の低下は、従業員の離職の増加につながります。従業員が少なくなることによって、残った従業員の負担が増加する点もデメリットの1つです。離職する従業員は増えると、労働力を補填するため新規採用も行う必要があります。その場合は、新しく入社した従業員への教育にリソースを割く必要性も出てくるでしょう。
帰属意識が低くなる原因
ここでは、社内において帰属意識が低くなる原因について解説します。
働き方が多様化している
リモートワークやフレックスタイム制など、働き方の多様化は帰属意識を低下させる要因の1つです。リモートワークの増加によって、以前よりも従業員同士が顔を合わせる機会・時間が少なくなりました。結果として、従業員の帰属意識が低くなりやすい環境になっています。また、終身雇用が当たり前ではない今、同じ企業で働き続ける人が少なくなっている点も要因として挙げられます。
企業理念やビジョンが伝わっていない
企業理念やビジョン、事業の方向性が伝わっていないと帰属意識を高めることはできません。従業員が何をすべきかという方向性が定まっていなければ、仕事に対してやりがいや責任感を持ちにくいためです。そのため、経営陣は従業員が同じ方向を目指して努力するための取り組みを行う必要があるでしょう。
コミュニケーションが不足している
社内でのコミュニケーションが不足していると、帰属意識が低くなります。帰属意識を高めるためにも、社内コミュニケーションの活性化を図ることをおすすめします。上司と部下、同僚同士、他部署との関わりを厚くすると、社内での居心地が良くなるでしょう。
評価制度に不満を持たれている
従業員が社内の評価制度に不満を持っていると、帰属意識が低くなります。「必要とされていない」「認められていない」といった思考は、従業員の帰属意識の低下を招きやすいため注意しましょう。帰属意識の低下を防ぐためにも、従業員の働き具合や努力、成果に対して、適切で公平な評価ができる体制を整える必要があります。
帰属意識を高める方法
ここでは、帰属意識を高める方法について解説します。
理念やビジョンを浸透させる
帰属意識を高める方法の一つ、企業の理念やビジョンを浸透させることです。従業員は、自分の業務が何につながっているのかが明確化されることで、帰属意識やモチベーションが高まります。理念・ビジョンを浸透させる具体的な方法としては、社内報の活用や動画の配信、ワークショップなどが挙げられるでしょう。
コミュニケーションの機会を増やす
社内でのコミュニケーションの機会を増やすことも帰属意識を高める方法の1つです。従業員は、互いにコミュニケーションを取るうちに仲間意識が生まれます。また、自身にない視点や発想、知識の増加、自身への刺激にもつながるでしょう。そのため、コミュニケーションの機会を積極的に増やす取り組みをおすすめします。
具体的な手法としては、コミュニケーションツールの導入、シャッフルランチの実施、オープンスペースやカフェスペースを設置するなどが挙げられます。
従業員の満足度を高める
従業員の満足度が高まると、会社への帰属意識も強くなります。従業員の満足度を高めるためには、福利厚生を充実させる、評価制度を見直す、柔軟な働き方を推進するなどの取り組みが重要です。また、従業員が成長できる機会の提供も大切であるため、スキル・キャリアアップの機会を用意しましょう。
帰属意識を高めることに成功した事例
ここでは、帰属意識を高めることに成功した事例を紹介します。
サイバーエージェント
帰属意識を高めることに成功した事例の1つは、サイバーエージェントの例です。サイバーエージェントでは、人材の「採用・育成・活性化・適材適所」を大切にしています。具体的には、従業員ごとの資質を把握し、能力を最大限に発揮できる配置にするなどの取り組みを行っている点が特徴です。
また、年齢や性別、経験を問わず管理職への登用も積極的に行っています。こういった取り組みを実施することで、帰属意識のアップに成功しました。結果として、サイバーエージェントは、離職率がわずか8.4%という業界水準と比べて低い数値を実現しています。
オリエンタルランド
帰属意識を高めることに成功した事例の1つは、オリエンタルランドによる事例です。オリエンタルランドは、従業員の離職率が低いことで知られています。従業員のモチベーションを向上させるために、下記をはじめとするするさまざまな取り組みを行っているのが特徴です。
【取り組みの具体例】
・功績に応じて記念品を贈呈する
・サービス・アワードプログラム:勤続年数に応じて特典を渡す
など
このような取り組みによって、入社した従業員の3年後離職率が0%の年があるほど、高い効果を発揮しています。
帰属意識を高める際の注意点
ここでは、帰属意識を高める際の注意点について解説します。
強制しない
帰属意識を高める際の注意点は、帰属意識の向上を強制しないことです。帰属意識を高めたいあまりに、強引に強制的な取り組みを行うことは、かえって逆効果になります。実施した取り組みを押し付けと感じる従業員が出てくるなど、従業員にストレスを与えてしまうことが考えられるため、注意が必要です。
終身雇用が当たり前だった時代のように、従業員が企業に対して、全面的な忠誠心を持っているわけではないことは理解しておきましょう。
組織課題を解決する取り組みも進める
帰属意識の向上には、組織課題を解決する取り組みも同時に進めることが重要です。組織課題が改善できていないまま、帰属意識を高める施策を打っても、十分な成果は出にくいでしょう。そのため、たとえば長時間労働や過大な業務量が原因で帰属意識が下がっている場合は、まずはそれらをなくす取り組みを図ることが大切です。
組織課題を解決する際には、解決のためにどの施策を実施するかについて優先順位をつけるとよいでしょう。
まとめ
帰属意識を高めることで、従業員のパフォーマンスがアップします。自社にあったやり方で帰属意識の向上を図りましょう。
帰属意識向上には従業員の悩みに寄り添うことも効果があります。例えば従業員のお金の悩み解消をサポートするなど、金融の側面からのサポートは、従業員に安心感を与え、企業に対する信頼感を高めることにつながるでしょう。オンアドでは「従業員のお金の悩み解決」をサポートする「お金の福利厚生サービス」を提供しています。ご関心をお持ちの方は、ぜひお問合せください。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。