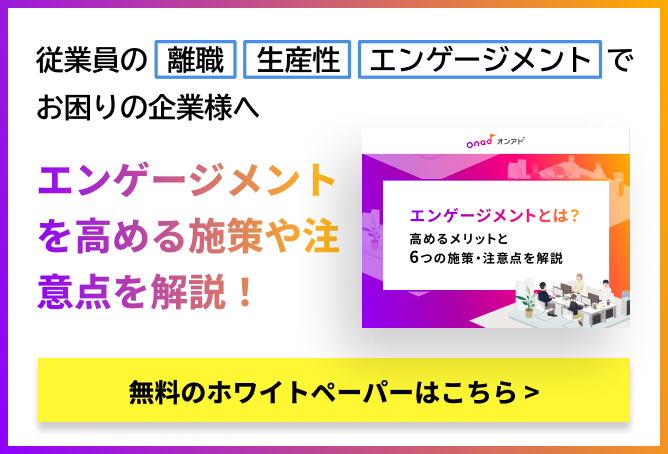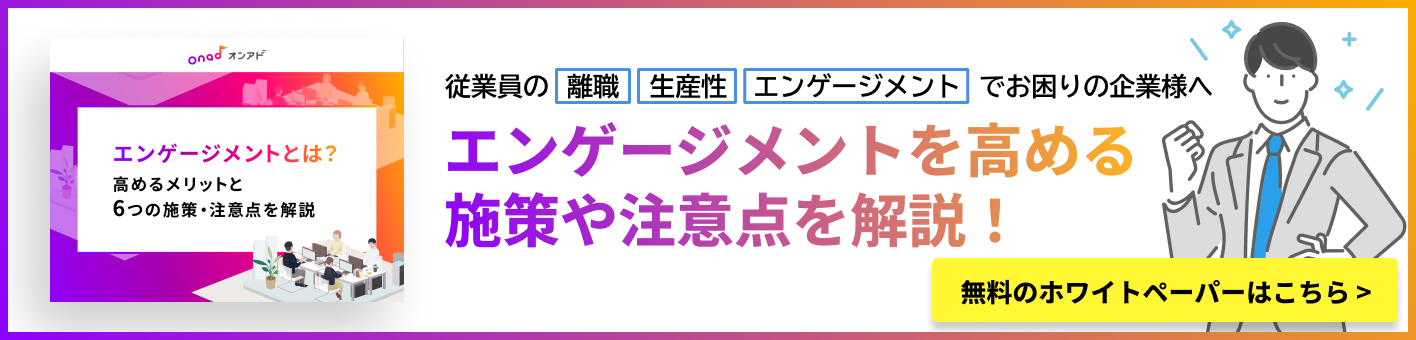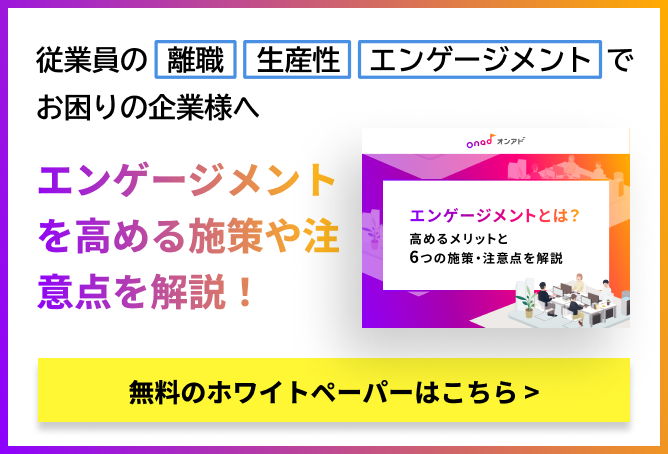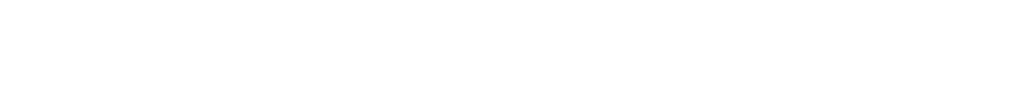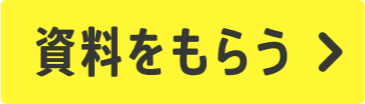SHARE
SHARE
愛社精神とエンゲージメントの違い|愛社精神を高めるメリット・デメリットや方法を解説
エンゲージメント |
「従業員に愛社精神を持ってほしい」と考える経営層や管理職層は多いでしょう。しかし、愛社精神を育むことには、メリットとデメリットが両方あり、どちらもしっかり把握することが大切です。また、愛社精神はエンゲージメントと混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。
本記事では、愛社精神とエンゲージメントとの違いや、愛社精神を高めるメリット・デメリット、具体的な方法などを解説します。
目次
愛社精神とは?
愛社精神とは、勤め先の会社を愛する気持ちのことです。会社に愛社精神を持つ理由は、人それぞれ異なります。愛社精神が育まれると、自分の仕事に誇りを持つことが可能です。結果的に、従業員が「会社に貢献したい」という気持ちが高まります。
愛社精神とエンゲージメントの違い
愛社精神とエンゲージメントは同じものとして混同されることもありますが、厳密には異なります。
エンゲージメントとは、従業員と会社のつながりや信頼関係のことです。愛社精神と同様に、従業員のエンゲージメントが高いと、会社に対する貢献意欲が高まります。
愛社精神は従業員から会社に対する気持ちであるのに対し、エンゲージメントは従業員と会社の双方向の関係性によって成り立つという違いがあります。また、エンゲージメントは従業員が会社の企業理念や方向性に共感することで高まりますが、愛社精神は必ずしも企業理念や方向性に共感することに起因するとは限りません。
このような違いはあるものの、従業員のエンゲージメントが高いと、愛社精神を高めることにもつながるため、両者には密接なかかわりがあります。
日本では愛社精神を持てない人が多い?
愛社精神が強ければ、現在の会社で生涯働きたいという意識が高まるはずです。
しかし、dodaが実施した調査によると、いま現在転職を考えている人は24.0%と、約4人に1人が転職を検討していることが明らかになっています。また、いま現在は転職を考えていない人でも、過去に転職活動をしたことがある人は41.1%、転職活動はしなかったが転職を考えたことのある人は27.3%と、多くの人が一度は転職を検討したことがあるようです。
また、世界各国のビジネスパーソンのエンゲージメントに関する調査では、日本の順位は各国と比べて低いことが分かっており、「日本人は愛社精神が強い」とは言い切れない傾向が見て取れます。
※参照:ビジネスパーソン2,000人の転職意識調査|doda
働く人の愛社精神が低下する理由
日本人の愛社精神が低下している背景には、以下のような理由が考えられます。
自身のキャリアや待遇を重視する人が増えている
海外では、自身のキャリアや待遇を求めて会社を選ぶという考え方が主流です。特にアメリカでは、業界や職種の垣根を超えたキャリアチェンジも少なくないようです。近年、日本でもこのような考え方が浸透しつつあり、1つの会社に長く勤める人ばかりでなく、キャリアアップやキャリアチェンジを目的とした転職に挑戦する人が増えています。
終身雇用制度の崩壊も関係している
終身雇用制度の崩壊も、働く人の愛社精神が低下している理由の1つです。終身雇用が当たり前だった時代とは異なり、現代は「愛社精神を持ち、1つの会社に生涯勤め上げる」という価値観が支配的ではなくなりつつあります。
従業員の愛社精神を高めるメリット
従業員の愛社精神を高めるメリットは、主に次の3つです。
離職率の低下につながる
愛社精神が高い従業員は、会社に対して愛着があるため、転職を考える可能性が低いと考えられます。従業員の愛社精神を高めることにより、人材の流出を防ぐことができ、採用・教育コストの削減にもつながるでしょう。
モチベーションが高まる
愛社精神が高い従業員は、会社の成長のために自主性を持って働くようになります。仕事に対するモチベーションが高まり、日々の業務に意欲的に取り組めるようになるでしょう。また、前向きに働く姿はまわりにも良い影響を与え、ほかの従業員のモチベーションにもプラスに働きます。
パフォーマンスが向上する
愛社精神が高まり、仕事にやりがいを感じられるようになれば、従業員の生産性もおのずと向上します。従業員1人ひとりのパフォーマンスが高まれば、売上の増加や顧客満足度の向上といった形で、会社としての成長にもつながるでしょう。
従業員の愛社精神を高めるデメリット
従業員の愛社精神が向上することでさまざまなメリットが期待できる一方、デメリットがあることも理解しておく必要があります。
人間関係のしがらみが生まれやすい
愛社精神が高い従業員が増えると、社内に一体感が生まれていきます。しかし、人間関係が深まると、さまざまなしがらみが生まれてしまうものです。職場の人間関係を重視するあまり、しがらみの多さに疲弊してしまう人が現れる恐れもあります。
馴れ合いにより、意見や指摘がしづらくなる
従業員の結束がマイナス方向に働くと、馴れ合いにより意見や指摘がしづらくなる場合があります。新しい知見を取り入れたり、改善点を指摘したりといったことができなくなると、会社の成長も阻害されてしまうでしょう。さらに、盲目的になるあまり不正に手を染めたり、自浄作用が働かなくなったりする恐れもあります。
従業員の愛社精神を高める方法
従業員の愛社精神を高めるなら、以下のような施策がおすすめです。
会社の理念を浸透させる
会社の経営理念や今後のビジョンを伝えると、会社の方針に納得感が生まれ、自分の仕事に意義を見いだしやすくなります。理念やビジョンの共有は会社への信頼感にもつながり、愛社精神が育まれていく土台となるでしょう。
行動指針を定め、周知する
行動指針とは、経営理念を実現するために必要な行動を明文化したものです。経営理念とセットで定めることで、従業員は自然と会社の理念に合わせた行動ができるようになり、愛社精神の醸成につながります。
人事評価制度を見直す
自分の仕事ぶりや頑張りが適切に評価されていると感じると、従業員は会社に信頼感を抱きやすくなります。「自分は会社にとって必要な存在」という実感を得られれば、会社への貢献意欲、愛社精神も高まることが期待できます。
福利厚生を充実させる
福利厚生は、従業員の生活の質の向上に直結するものです。福利厚生が充実している職場では、従業員が安心して働けるようになり、愛社精神が育まれやすくなります。各種社会保険への対応はもちろん、サークル活動への補助金やアニバーサリー休暇などのユニークな仕組みをつくることもおすすめです。
従業員との丁寧なコミュニケーション
愛社精神を育むためには、従業員1人ひとりと丁寧にコミュニケーションをとることが重要です。直属の上司や人事部が目を配りながら、定期面談などを実施し、適切な関係構築を進めましょう。「会社や上司から気にかけてもらえている」と実感できることが、愛社精神を育むことにつながります。
従業員の愛社精神を育むうえでの注意点
従業員の愛社精神を育む際は、以下のポイントに注意しましょう。
愛社精神を強要しない
愛社精神は自然と育まれるべきものであり、会社が強要するものではありません。会社としては愛社精神を押し付けるのではなく、愛社精神を持ってもらえるような風土を醸成していくことが大切です。また、愛社精神が強いあまり、従業員がほかの従業員にも愛社精神を強要することがないよう注意する必要があります。
自社を客観的に評価することも大切である
愛社精神があまりに強すぎると、会社の課題を見逃してしまう恐れがあります。従業員の愛社精神を高めつつも、自社を客観的に評価し、課題解決に取り組む姿勢を保つことが大切です。
労働環境とは切り分けて考える
「愛社精神があれば、会社のために身を粉にして働けるはず」といったように、愛社精神を盾にして、従業員に長時間労働やサービス残業を強いてはなりません。従業員の心身の健康を守るために、愛社精神と労働環境とは切り分けて考えるべきです。また、愛社精神が高すぎるあまり、従業員が無理な働き方をしていないかどうかもチェックする必要があります。
愛社精神だけでなくエンゲージメントの向上も重要
愛社精神とエンゲージメントは厳密には異なる概念ですが、それぞれ密接な関係があります。従業員のエンゲージメントを高めることで、愛社精神が育まれることもあれば、愛社精神を育むための取り組みが、従業員のエンゲージメントを高めることもあるでしょう。愛社精神という、従業員から会社に対する一方的な気持ちにだけ期待するのではなく、経営理念の浸透や社内コミュニケーションの活性化、透明性・公平性の高い人事評価制度の構築などを通し、従業員と会社間の双方向の信頼関係を高めることが大切です。
まとめ
愛社精神とエンゲージメントは同じものとされる場合もありますが、愛社精神は従業員から会社への一方的な気持ちなのに対し、エンゲージメントは従業員と会社の双方向のつながりを表します。愛社精神やエンゲージメントを高めることは、会社にとってさまざまなメリットをもたらしますが、一定のリスクも存在するため注意が必要です。メリット・デメリットを両方把握したうえで自社の状況にあった施策に取り組みましょう。 愛社精神を高める施策として、従業員のファイナンシャル・ウェルネスに着目することもおすすめです。ファイナンシャル・ウェルネスの向上を目指すなら、株式会社オンアドまでご相談ください。実績豊富な金融相談のプロが「従業員のお金の悩み解決」を通じて、愛社精神やエンゲージメント向上を支援します。オンアドの「お金の福利厚生サービス」にご関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。