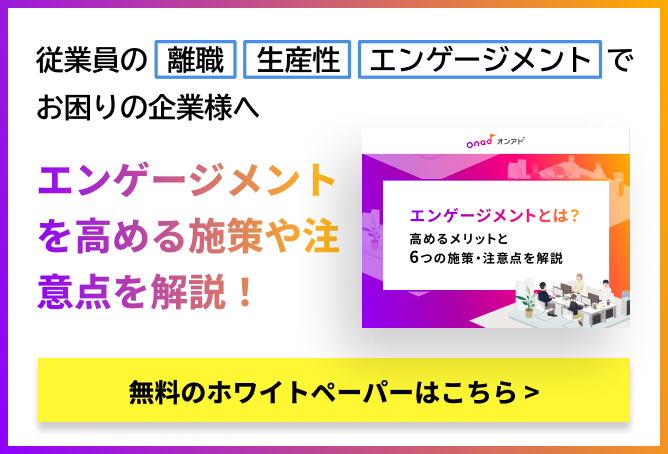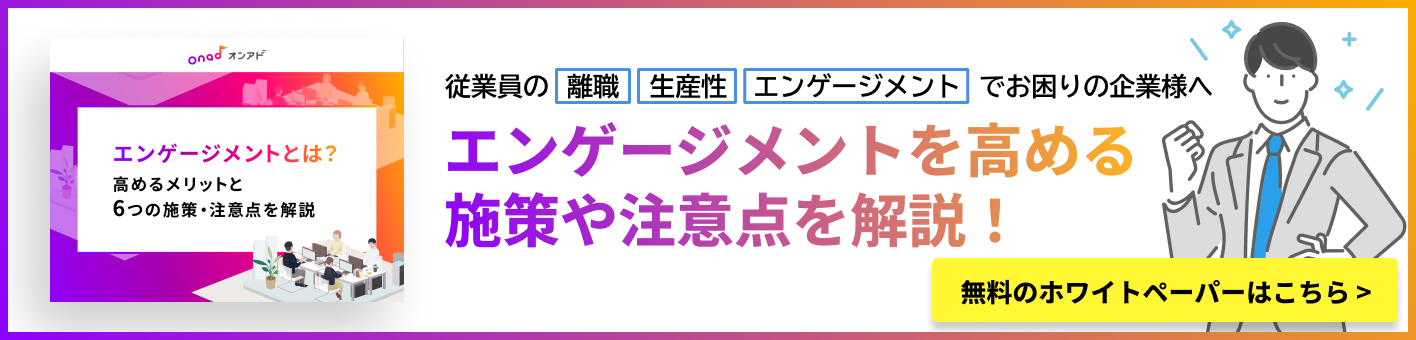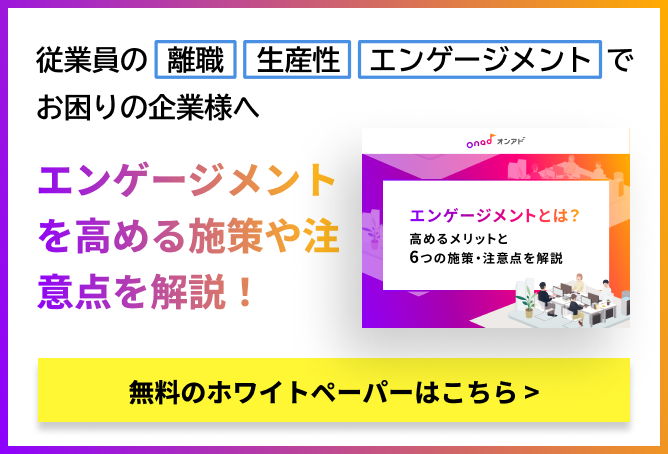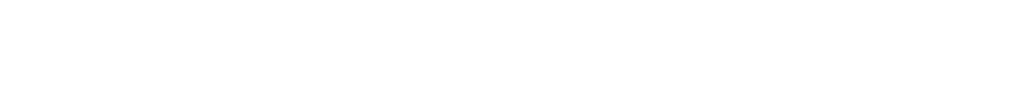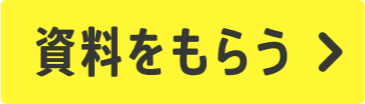SHARE
SHARE
エンゲージメントの醸成とは?言葉の定義やメリット、具体的な施策まで詳しく解説
エンゲージメント |
会社が成長するためには、エンゲージメントを醸成させることが大切とされています。近年、日本でも注目を集めているエンゲージメントですが、「エンゲージメントを醸成する」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
本記事では、「エンゲージメントの醸成」という言葉の定義や、エンゲージメントを醸成するメリット、具体的な施策などについて解説します。
目次
「エンゲージメントを醸成する」とは
近年よく耳にする「エンゲージメントを醸成する」とは、一体どのような行為を指すのでしょうか。ここではまず、「エンゲージメントを熟成する」の定義について、解説します。
「醸成」の意味
醸成とは、もともと「原料を発酵させ、酒や調味料をつくること」「風土や考え方がだんだんと形成されること」といった意味を持つ言葉です。ビジネスシーンでは、主に後者の意味で用いられることが多く、組織文化や共通する考え方、仲間意識などが、時間をかけて徐々に作られていくことを意味します。
「エンゲージメント」の意味
「エンゲージメント(engagement)」とは、本来「約束」や「契約」、「誓約」、「婚約」などを意味する言葉です。ビジネスシーンにおいては、主に双方間の深いつながりを指す場合に用いられます。
ビジネスにおけるエンゲージメントの種類
ビジネスシーンで使用されるエンゲージメントには、主に次の3種類があります。
| 従業員エンゲージメント | 会社と従業員の間のつながり |
| 顧客エンゲージメント | 会社と顧客の間のつながり |
| ワークエンゲージメント | 従業員が仕事に対してポジティブに取り組めている心理状態 |
ビジネスにおける「エンゲージメントの醸成」の意味
ビジネスシーンにおいて、「エンゲージメントの醸成」という言葉が使用されるときは、基本的に従業員エンゲージメントを指す場合が多いです。会社と従業員の双方間のつながりを形成し、自社への愛着や貢献意欲を高めていくことを表します。
「醸成」とは、時間をかけて会社の文化や風土を徐々に作り上げていくイメージです。そのため、「エンゲージメントを高める」という表現と比べると、「エンゲージメントを醸成する」という表現は、組織全体の根本的な意識改革を促すニュアンスが強いといえるでしょう。
エンゲージメントと類似語の違い
エンゲージメントには、いくつか混同されやすい類似語があります。ここでは、エンゲージメントと混同されやすい用語の意味を解説します。
モチベーションとの違い
「モチベーション(motivation)」とは、行動を起こすための意欲を指す言葉です。ビジネスにおいては、仕事のやりがいや達成感、ボーナスやインセンティブなどの報酬を目的に、従業員個人のなかで生まれる動機を指します。動機を生む要因は様々であり、必ずしも会社への貢献意欲が起点となっているわけではありません。
エンゲージメントは、会社や組織との信頼関係をベースとした、貢献意欲が高い状態を意味する概念です。両者は異なる意味合いを持ってはいますが、従業員のエンゲージメントを醸成することによって、従業員のモチベーション向上も期待できるでしょう。
コミットメントとの違い
エンゲージメントと混同されやすい言葉の1つに「コミットメント(commitment)」があります。コミットメントは、エンゲージメントと比べて「責任」というニュアンスが強いのがポイントです。コミットメントは、自分に与えられた仕事をやりきるために、責任感を持って取り組んでいる状態を指します。
従業員満足度との違い
「従業員満足度」も、エンゲージメントと混同されやすい用語の1つです。従業員満足度は、給与や福利厚生など、会社から与えられているものへの満足度を評価する指標です。従業員に気持ちよく働いてもらうために重要な指標の1つですが、あくまでも会社の制度や待遇などに対する満足度を表すものであるため、従業員の貢献意欲や自主性を測ることはできません。
従業員エンゲージメントが重視される3つの理由
近年、従業員エンゲージメントが重視される理由は、主に次の3つです。
労働者の価値観の多様化
労働者の価値観の変化にともない、仕事に対する考え方も多様化しています。近年は、多様な働き方が生まれたことで、所属する会社に依存せずとも、自分のキャリアを自律的に設計できるようになりました。従来の方法では、会社と従業員の結びつきを維持することが難しくなっているため、エンゲージメントに注目が集まっています。
人材の流動化
日本でも、海外のように実力主義・成果主義やジョブ型雇用を導入する会社が増加傾向です。より良い環境や待遇を求めて転職を検討する人が増え、人材の流動化が加速しています。人材の流出を防ぐため、従業員とのつながりを深める必要性が高まっていることも、エンゲージメントが重要視されている理由の1つです。
景気の低迷
内閣府が発表した2023年の名目国内総生産(GDP)は、ドル換算すると4兆2106億ドルで、世界4位に転落しました。日本の景気が低迷している要因の1つとして、日本人の生産性の低下が挙げられます。公益財団法人日本生産性本部の発表によると、2023年の日本の労働生産性はOECD(経済協力開発機構)加盟国38カ国中30位と、過去最低の結果でした。
このような背景を受け、会社の成長につなげるべく、エンゲージメントの醸成や従業員の生産性向上に、注目が集まっています。
※参照:統計表一覧(2023年10-12月期 1次速報値)|内閣府
従業員エンゲージメントを醸成するメリット
それでは一体、従業員エンゲージメントを醸成することで、一体どのようなメリットが得られるのでしょうか。従業員エンゲージメントを醸成すると、次のようなメリットを期待できます。
モチベーションや生産性の向上
一般的に、従業員エンゲージメントが高い会社では、従業員の仕事に対するモチベーションを、高い状態に維持しやすいとされています。エンゲージメントが高い従業員は、会社のために自発的に行動する傾向が強いため、生産性の向上にも期待できるでしょう。
顧客満足度の向上
エンゲージメントが高い従業員は、顧客に対してより良いサービスや商品を提供できるよう、自ら積極的に工夫するようになる傾向が強いです。より良いサービスや商品の提供は、顧客満足度の向上につながるため、結果として会社の売上アップが見込まれます。
離職率の低下
従業員のエンゲージメントが向上すると、会社への貢献意欲や「この会社で長く働きたい」という気持ちが高まります。従業員のエンゲージメントが高い会社では、従業員の離職率が低下し、人材流出を防ぐことが可能です。その結果、採用コストの削減にもつながります。
団結力が高まる
従業員エンゲージメントの向上は、職場の人間関係にもプラスの影響を与えます。従業員同士の信頼が深まることで、コミュニケーションが活性化され、団結力が高まります。団結力が高まることで、働きやすい環境を構築し、足並みを揃えて協力し合うことが可能です。
エンゲージメントを醸成する手順
エンゲージメントを醸成する具体的なプロセスは、次のとおりです。
1.エンゲージメントの定義を明確化する
2.現状把握(サーベイ)を行う
3.施策や制度設計を検討する
4.施策を実施し、PDCAサイクルを回す
まずは、自社にとって「エンゲージメントが高い従業員」とはどのような人物なのかを、具体的に思い描き、エンゲージメントの定義を明確化しましょう。次に、現状把握のためにエンゲージメント調査を実施し、施策や制度を設計します。施策を実施したあとは、定期的に効果測定を行い、PDCAサイクルを回すことも大切です。
従業員エンゲージメントを醸成する6つの施策
従業員エンゲージメントを醸成したい場合は、次のような施策がおすすめです。
1.経営理念やビジョンの共有
会社としての考えや方針を明確にして、向かうべき方向を従業員と共有しましょう。従業員が会社のビジョンを理解しながら仕事に取り組むことで、会社の方向性と自身の仕事の一体感が得られ、エンゲージメントの醸成につながります。
2.職場環境の整備
従業員一人ひとりの事情にできる範囲で配慮し、誰もが働きやすい職場環境を構築しましょう。オフィス環境を整えることはもちろん、多様なニーズに合わせて、柔軟な働き方に対応することも大切です。
3.従業員の成長をサポートする
会社が従業員の成長をサポートすることは、従業員のエンゲージメント情勢に効果的です。具体的には、O資格試験の取得支援や外部研修の受講費用を補助するなどの施策が考えられるでしょう。自社や従業員に合った、的確なサポートを選択することが重要です。
4.従業員の頑張りを適正に評価する
会社に自分の努力や成長が認められていると感じると、従業員の会社に対する信頼感や貢献意欲が高まります。そのためには、従業員の頑張りを正しく評価できる、透明性・公平性の高い人事評価制度を整えることが必要不可欠です。
5.社内コミュニケーションを活性化する
職場の人間関係が従業員エンゲージメントに与える影響は大きいものです。社内コミュニケーションを活性化して互いの信頼関係が深まれば、エンゲージメントの醸成につながります。部下とのワンオンワンミーティングや同僚とのランチミーティングなどを実施し、定期的に従業員とコミュニケーションを図ることで、従業員が抱えている悩みや考えを把握することが重要です。
6.心身の健康に気を配る
従業員本人や家族の心身の健康を支援することも、エンゲージメントの醸成につながります。具体的には、「定期健診の受診率を100%にする」「職場での運動機会の提供」「ストレスチェックを実施する」「メンタル不調者への配慮・支援体制を整える」といった取り組みが考えられるでしょう。
従業員エンゲージメントの調査方法
従業員エンゲージメントを醸成するためには、現状把握と定期的な測定が欠かせません。エンゲージメントの調査方法は、パルスサーベイとセンサスサーベイの2種類に分けられます。
| パルスサーベイ | 設問数の少ない調査を、比較的短いスパンで実施する方法 |
| センサスサーベイ | 設問数の多い調査を、比較的長いスパンで実施する方法 |
また、調査のやり方としては、自社で実施する場合と、外部に委託する場合があります。エンゲージメントを効率的に測定するために、エンゲージメントサーベイツールを提供している会社も多くあります。
従業員エンゲージメントを調査する際の注意点
エンゲージメント調査をより効果的に活用するために、次のようなポイントに注意しましょう。
負担の少ない方法にする
エンゲージメント調査を実施する際は、回答する従業員の負担に配慮し、設問数やUIに気を配ることが大切です。回答者の負担を軽減することは、回答率や正確性の向上につながります。
不利益にならないことを周知する
従業員から正直な回答を引き出すためには、「回答によって不利益を被ることはない」という信頼感を得ることが必要です。調査目的の周知や匿名で回答できるようにするなど、従業員が素直な心情を反映できるよう配慮したうえで、不利益にならないことを周知しましょう。
定期的に実施する
施策の効果を確認するためには、エンゲージメント調査を1回きりではなく、定期的に実施することが不可欠です。エンゲージメントサーベイの実施によって明らかになった課題があれば、その課題に対する解決策を検討・実施し、狙った効果が得られているかを確認していきましょう。PDCAを前提とした中長期的な取り組みとしてスタートすることが望ましいです。
エンゲージメントの醸成に取り組む企業事例
最後は、エンゲージメントの醸成に取り組む企業の事例をご紹介します。自社の従業員のエンゲージメントを醸成させる際のヒントとして、ぜひ役立ててください。
株式会社コンカー
株式会社コンカーは、「フィードバックする文化」と「高め合う文化」で、働きがいのある組織づくりを実現。オフサイトミーティング(ミニ合宿)や表彰イベントを実施したり、先輩従業員のサポートを受けながら若手従業員が社内イベントを企画・運営したりと、多種多様な取り組みを実施しています。
Sansan株式会社
Sansan株式会社では、従業員に対して定期的なエンゲージメント調査を実施し、低下が見られた場合は適切に対処しています。同社は、リモートワークでビジネス職のエンゲージメントに低下が見られた際に、ツールの導入によって社内コミュニケーションを活性化させました。このような対策により、従業員エンゲージメントの向上につなげることに成功しています。
まとめ
エンゲージメントを醸成すると、従業員のモチベーションが高まったり、離職率の低下につながったりと、さまざまなメリットが期待できます。価値観の多様化や景気の低迷などにともない、エンゲージメントの重要性がますます高まっているなか、今回紹介した施策を参考に、従業員エンゲージメントの醸成に取り組んでみてはいかがでしょうか。
従業員エンゲージメントを醸成する施策の1つとして、「ファイナンシャル・ウェルネス」(お金の健康)にも注目が集まっています。株式会社オンアドでは、従業員エンゲージメントの醸成に役立つ、金融教育動画コンテンツ・ウェブセミナー・資産管理アプリ・従業員向け個別相談を提供しています。ご関心をお持ちの方はお気軽にお問合せください。
この記事を監修した人

株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。

この記事を監修した人
株式会社オンアド
株式会社オンアドは野村ホールディングス、千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行の4社により設立された投資助言会社です。「すべての人が最善のアドバイスにより、理想の未来をかたちにする」というビジョンのもと、商品販売を一切行わず、アドバイスに特化した新しい金融サービスをオンライン完結でご提供します。